【この記事で解決できるお悩み】
「カルピスバター」ってどんなバター?
普通のバターとは何が違うの?
おすすめの使い方やレシピ、注意点をおしえて!



この記事では、こんなお悩みを解決します!
一度食べたらやみつきになるとウワサの、カルピスバター。
1963年(昭和38年)の発売以来のロングセラーで、未だに人気があり過ぎて買えないことも多い幻のバターです。
その色は豆腐のようにまっしろで、一体何が入っているのか、疑問に思う方も多いみたい。
そこで今回は、カルピス社が販売するカルピスバターを徹底解説!
普通のバターとの違いや、おすすめの使い方・注意点を整理してみました。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/


この記事を書いた人:
腸活研究家 長谷川ろみ
発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら
カルピスバターとは?


カルピスバターの特徴は、以下のとおり。
一つずつ見ていきましょう。
希少性が高い「幻のバター」
カルピスバターの歴史は古く、発売はなんと1963年(昭和38年)。
乳酸菌飲料のカルピスを作る過程で生まれる脂肪分を使って、業務用にレストラン、菓子店、ホテルなどに提供したのがはじまりです。
カルピスバターの濃厚な風味が、フランス産のバターに似ているとのことから、フランス料理の一流シェフたちに愛され、業務用のバターとして人気を博しました。
その後、1981年には一般消費者向けに「カルピス(株)特撰バター」を販売。
そのおいしさから大人気になりますが、そもそも「カルピス(株)特撰バター」は、大量生産はむずかしい貴重品。



乳酸菌飲料のカルピス(470ml)を約40本を作る過程で、やっと1個のバターができるんだって。
一般消費者の手にはなかなか渡らなかったため、「幻のバター」と呼ばれました。
乳酸菌飲料の「カルピス」から作られる
カルピスバターは、乳酸菌飲料の「カルピス」を作る時にできる脂肪分から作られています。
原材料は、生乳のみ。
生乳からクリームと水分を分離し、そのクリームを撹拌して、脂肪のみをかためて、練り上げるのだとか。
【カルピスができるまで】
原料乳+カルピス菌
↓
1次発酵
↓
酸乳+砂糖
↓
2次発酵
↓
仕上げ



全く無駄になるところがない!さすがカルピス!!カルピス用の品質の良い牛乳からできる脂肪分を使うことで、ツヤ、風味、色など、全てにおいて品質の高いバターになります。
カルピス社のホームページでは、バターの歴史を以下のように説明しています。
カルピス社のバターは、100年以上飲み継がれてきた乳酸菌飲料カルピス®をつくる工程で生乳から乳脂肪を分離する時にできる脂肪分(クリーム分)からうまれたのが始まりです。
(※1)カルピス社バターの歴史|カルピス株式会社特選バター
日本人好みのさわやかなコクと香りを生み出すことができる厳選された乳酸菌を使用しているため、フレッシュな印象が強いバターに仕上がっています。



後味もびっくりするほどすっきりで、バターじゃないみたいなんです。
特徴は白い色となめらかな舌触り
カルピスバターの大きな特徴は、さわやかな風味となめらかな舌触り。



ちょっとクリームチーズっぽいかも?舌触りがなめらかなのは、乳脂肪分が普通のバターよりも多めなのも関係しているようです。
| カルピスバター | 一般の無発酵バター | 一般の発酵バター | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 744kcal | 700kcal | 713kcal |
| タンパク質 | 0.3~0.7g | 0.6g | 0.6g |
| 脂質 | 82.2g | 81.0g | 80.0g |
| 炭水化物 | 0~1.1g | 0.2g | 4.4g |
| 食塩相当量 | 1.5g | 1.9g | 1.3g |


\ 一流シェフ・パティシエにも愛用者多数(*´▽`*)/
普通のバターとの違いは?


カルピスバターを実際に食べてみて、わたしが感じた味・香り・見た目の特徴は、以下のとおり。
普通のバターとは全く違う味・香り・見た目をしています。
| カルピスバター | |
|---|---|
| 味 | ・濃厚なコクがあり、クリーミー。ミルク感が強い ・酸味もあり、後味はさっぱり/すっきりしている ・塩気は程よくひかえめ ・なめらかな口当たりと透き通る口どけ ・生クリームとバターの中間? ・クセがないのでなんにでも合わせやすい |
| 香り | ・甘いミルクの香り ・他の香りを邪魔しないので、塩味が強い料理にもあう |
| 見た目 | ・白い |



普通のバターというより、生クリームとバターの間のような印象があります。
発酵バターとの違い
カルピスバターは、その濃厚なコクが共通しているため発酵バターの一種だと思われることが多いようです。
でも、すべてのカルピスバターが発酵バターというわけではありません。
カルピスバターには発酵と非発酵の両方のタイプがあります。
発酵バター:カルピス(株)発酵バター
非発酵バター:カルピス(株)バター、カルピス(株)特撰バター



いちばんよく使われている「カルピス(株)特撰バター」は、発酵していません。
一般的な発酵バターは、発酵前に乳酸菌を添加して作ります。
しかし、カルピスバターは途中で乳酸菌を添加することはありません。



でもカルピスを作る過程では乳酸菌を使っているので、そのあたりと混同されて、発酵バターだと思われているのかも!


\ 一流シェフ・パティシエにも愛用者多数(*´▽`*)/
エシレバターとの違い


カルピスバターは、フランス産の高級発酵バターである「エシレバター」と似ていると思われがちです。
発酵バターの本場であるフランスのブランドで、認可されるのが難しいと言われる「AOP」の証が表示された一流品。
AOPバター
=1992年に生まれたヨーロッパのバターに関する認証制度
=20件の酪農家の生乳が原料+伝統の製造プロセスが守られていることが条件
=「A:Appellation(名称)」「O:Origine(原産地)」「P:Protegee(守られている)」の頭文字
ワインやチーズのように産地がわかり、一流品の区別がつくように、作られたバターの認証制度です。
カルピスバターに似たさっぱりとした酸味がありますが、発酵バターであることから芳醇なバターの香りが強く、あっさりさわやかな印象のカルピスバターとは少し印象が異なります。
またエシレバターは乳酸菌を途中で添加していることからも、プロピオン酸や酪酸などの有機酸が多く含まれ、濃厚な香りが特徴のバターとなっています。



個人的には濃厚なコクがあるほうが好きな方はエシレバター派が多く、さっぱりミルキーが好きな方はカルピスバター派の方が多い印象があります。酪酸についてもっと知りたい方は、この記事も読んでみてね。
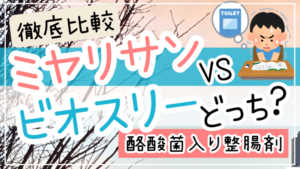
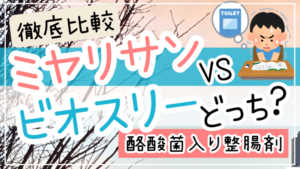
カルピスバターに関するよくある質問


カルピスバターに関するよくある質問をまとめました。
ひとつずつ見ていきましょう。
カルピスバターはなぜ白いの?
カルピスバターが白い理由は、カロテンの量が少ない干し草や穀物飼料を食べた牛の生乳を使っているからです。
乳牛が食べたエサに含まれるカロテンの量によって、バターの色は変化すると言われています。
カロテンの量が多い青草を食べた牛の生乳が原料→黄色っぽくなる
カロテンの量が少ない干し草や穀物飼料を食べた牛の生乳が原料→白っぽくなる
カルピスバターの原料を作る乳牛は、干し草の他に、とうもろこしや麦、大豆などをブレンドした飼料を食べているとのこと(※3)。
色にも特徴があり、北海道産のバターに比べるとかなり白い。それは、カルピスバターが群馬と岡山の工場で生産されていて、その周辺の乳牛の生乳を使っているから。北海道の乳牛が主に青草を食べているのに対し、これらの乳牛は干し草の他に、とうもろこしや麦、大豆などをブレンドした飼料を食べている。要はエサの違いが製品の色の違いになっているというのが会社側の説明だ。
(※3)カルピスバターを「幻」にする日本の酪農行政|東洋経済



このエサの違いが、お豆腐みたいな白い色の原因のひとつのようです。
カルピスバターの値段は?
カルピスバターの値段は、一般的なバターと比べるとかなりお高め。
内容量:450g
メーカー希望小売価格:1,590円
これは乳酸菌飲料のカルピス(470ml)を約40本を作る過程で、やっと1個のバターができるという希少性によるもの。
大量にバターを使う料理に使ってしまうのはもったいないかもしれませんが、香りや風味をつけたい時や、そのままパンにつけて食べる時などは、ちょっと使うだけで料理の質がぐんとアップするのでおすすめです。
カルピス特選バターと業務用の違いは?
一般消費者用のカルピス特選バターと業務用のカルピスバターの中身は同じものです。
一般消費者向け:カルピス特選バター
企業消費者向け:カルピスバター業務用
ただし一般消費者向けのカルピス特選バターが有塩・食塩不使用の2種類であるのに対し、業務用バターはカルピスバター、カルピス発酵バター、カルピス低水分バターと大きく3種類に分けられています。



業務用から販売が始まったカルピスバターは、今現在も業務用の方が種類が豊富なんですね。
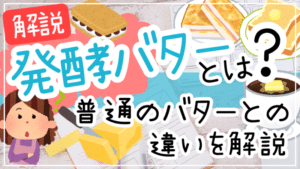
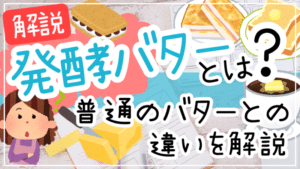
カルピスバターの美味しい使い方


カルピスバターは、ある程度高級品のため、香りや味を楽しみにくい食べ方・使い方をするともったいないかもしれません。
おすすめの美味しい使い方は、以下のとおり。
一つずつ見ていきましょう。
焼きたてのトーストに塗るのが最強!
カルピスバターを購入したらまず試したいのが、焼きたてのトーストに塗って食べる食べ方です。



とてもシンプルですが、カルピスバターの味がいちばんわかりやすい食べ方です。
さいしょはジャムや甘味料とは合わせずに、カルピスバターだけで食べてみてください。
十分な甘みとさわやかな酸味が感じられるはずです。
トーストにカルピスバターを合わせる時は、厚切りトーストがおすすめです。
じゅわっとバターが染み込むぐらい多めにのせると、カルピスバターの濃厚な風味がより深く感じられます。



慣れてきたら、小豆あんと合わせて小倉トーストにするのもおすすめ!
さわやかな酸味がお菓子作りに最適
カルピスバターは甘みのある香りとさわやかな酸味が特徴的なので、甘いお菓子にも向いています。
スコーン、クッキーなどの焼き菓子に使ってももちろんおいしいですが、濃厚で芳醇な香りを期待するなら、カルピスバターより発酵バターのほうがおすすめ。
カルピスバターは、発酵バターよりもさらにさわやかな風味が特徴的なので、火を通さないで新鮮なままクリームに使ったり、さわやかな風味を生かした使い方がさらにおすすめです。
さわやかなレモンを使ったケーキ
さっぱりとしたチーズケーキ
バタークリームを使ったマフィンやロールケーキ
またまっしろな色を活かして、クリームを着色して飾りに使うこともできます。



かわいいお菓子ができそうだ…!
じゃがバターやさつまいもにつけて食べると美味
カルピスバターは、さっぱりしたやさしい甘さがしつこくないので、ちょっとした風味付けに向いています。
特にじゃがバターや干し芋などのいも類へのちょい足しは、はずれがありません。
ほくほくの熱いじゃがいもやさつまいもにカルピスバターをたっぷりかけるだけで、贅沢な料理が完成します。



いも好きの方にはぜひやってみてほしいです!個人的にいちばん好きな食べ方かも…ほぼ調理なしでイケるので、ずぼらさんにもおすすめ。笑
ラーメンやうどんにちょっとのせてもおいしい
カルピスバターは甘いものとの相性がよいと思われがちですが、クセがないので塩味が強いものとも驚くほど相性が良くなります。
例えば、ラーメンやうどんなどにちょっとのせるだけで、まったく違う味に変化します。



うわぁ、おいしそう!!おうちでうどんをゆでて、カルピスバターを絡めるだけで、めちゃくちゃおいしくなります。
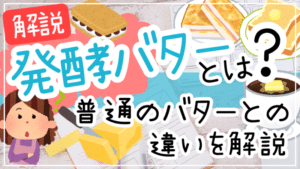
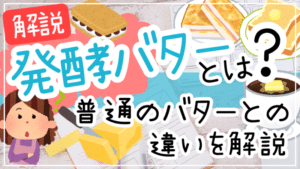
カルピスバターの購入方法と取扱店


カルピスバターは売り切れ続出の人気商品ではありますが、以下の方法で手に入れることが可能です。
一つずつ見ていきましょう。
高級スーパーで購入可能
カルピスバターは、以下のような高級スーパーで購入することが可能です。
場合によっては、小さい50gパックで買うこともできるので、一人暮らしの方でも買いやすいかもしれません。
カルディ
コストコ
成城石井
明治屋 など



特にカルディでよく見つけることが多い気がするんだけど…みなさんのご自宅の周りではどうですか?ただ、全種類がおいてあることはめったにない気がします…



小さいサイズの特選バターは、かなり便利!品薄になることも多いので、見つけたら買いかも?!笑
ネット通販でも購入可能
カルピスバターは、Amazonや楽天市場などのネット通販でも購入することができます。


\ 一流シェフ・パティシエにも愛用者多数(*´▽`*)/



ネットなら業務用の発酵バターも購入できます!


\ 一流シェフ・パティシエにも愛用者多数(*´▽`*)/
まとめ:カルピスバターとは?普通のバターとの違いを解説!おすすめの使い方


一度食べたらやみつきになるとウワサの、カルピスバター。
1963年(昭和38年)の発売以来のロングセラーで、未だに人気があり過ぎて買えないことも多い幻のバターです。
カルピスバターの特徴は、以下のとおり。
普通のバターとは全く違う味・香り・見た目をしていて、バターと生クリームの間のような印象があります。
| カルピスバター | |
|---|---|
| 味 | ・濃厚なコクがあり、クリーミー。ミルク感が強い ・酸味もあり、後味はさっぱり/すっきりしている ・塩気は程よくひかえめ ・なめらかな口当たりと透き通る口どけ ・生クリームとバターの中間? ・クセがないのでなんにでも合わせやすい |
| 香り | ・甘いミルクの香り ・他の香りを邪魔しないので、塩味が強い料理にもあう |
| 見た目 | ・白い |
おすすめの美味しい使い方は、以下のとおり。
カルピスバターは少し効果なので、大量に料理に練りこんで使うというよりも、ちょい足しで香りや風味を楽しむのがおすすめです。
微生物の発酵のちからでますますおいしく、体にやさしいバターになるおもしろい例をご紹介しました。
発酵のしくみや発酵菌が気になる方は、発酵ライフアドバイザー資格講座もおすすめです。
参考にしてみてね。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/
参考文献
(※1)カルピス社バターの歴史|カルピス株式会社特選バター
https://calpis-butter.jp/about/
(※2)日本食品標準成分表2020年版(八訂)
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html
(※3)カルピスバターを「幻」にする日本の酪農行政|東洋経済
https://toyokeizai.net/articles/-/116932?page=2










