【この記事で解決できるお悩み】
・みりんがない!なにで代用するのがいちばんいいの?
・みりんも日本酒もない!それでもみりんの代用はできる?



この記事では、こんなお悩みを解決します!
和食をおいしくする定番の発酵調味料、みりん。
自炊するならぜひそろえておきたい定番の調味料ではありますが、料理をあまりしない人にとっては、正直いって謎が多い調味料。
料理中に「あ…みりんがない…!」と気がついたとしても、どの調味料で代用するのがいいのか、迷ってしまう方も多いみたい。
そこで今回は、みりんがない時の代用法を徹底解説!
一般的に代用しやすいと言われる日本酒を使った代用法から、日本酒がない時でも心配いらない隠れ技まで、まるっとまとめてみました。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/


この記事を書いた人:
腸活研究家 長谷川ろみ
発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら
みりんの代用は日本酒+糖類がベスト【難易度:低】


みりんが家にない時は、日本酒+糖類で代用するのが基本です。
みりん=日本酒+糖類
他にもいろんな方法がありますが、いちばん難易度が低いのが日本酒をベースにする方法。
それでは詳しく見ていきましょう。
日本酒がみりんの代用に適している理由
日本酒がみりんの代用に適している理由は、みりんと日本酒の成分がとても似ているからです。
みりん
=もち米と米麹を発酵させた「アルコール」+ぶどう糖やオリゴ糖などの「糖分」
日本酒
=米と米麹を発酵させた「アルコール」



酒税法では、みりんは酒類の一種に分類されています。たしかにそっくり。
一方、日本酒も米と米麹を原料として発酵させて作るため、「アルコール」はみりんと同じく14%程度です。
みりんの代用品として日本酒がすぐれている理由は、アルコールの量や度数だけではありません。
塩分や甘みなどの味や色も、みりんと日本酒は比較的近いのです。
みりんの代用品として候補に挙がりやすい酒類と比べてみると、以下のとおり。
| 色 | 塩分 | 甘み | アルコール度数 | 総合点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| みりん | 薄い黄・茶 | 14% | ー | ||
| 日本酒 | 透明 | 14% | |||
| 料理酒 | 薄い黄・茶 | 14% | |||
| 白ワイン | 透明 | 10~15% | |||
| 赤ワイン | 赤 | 10~15% | |||
| 焼酎 | 透明 | 25% | |||
| 梅酒 | 薄い黄・茶 | 10~15% | |||
| 紹興酒 | 濃い茶 | 14~18% |
真っ赤な色が特徴の赤ワインや濃い茶色の紹興酒は、色が濃いせいで料理の邪魔をする可能性があります。
またぶどうや梅などのフルーツが原料に含まれるワインや梅酒は、果物独特の甘みが強く、代用品としては適しません。
さらに料理酒は比較的条件が近いのですが、塩が含まれている商品も多く、代用どころか、まったく違う味になってしまう可能性もあります。
日本酒
=色・塩分・甘み・アルコール度数すべてにおいて大きな差がない
料理酒
=塩分が多い
(料理の塩分調整ができれば代用できる)
白ワイン
=甘みと酸味が邪魔しがち
(料理の甘み調整ができれば代用できる)
赤ワイン
=赤い色が濃く、料理の色が変わってしまう
焼酎
=アルコール度数が高すぎる
(アルコールを飛ばせば代用できる)
梅酒
=甘みと酸味が邪魔しがち



米の甘さ=ぶどう糖、オリゴ糖とフルーツの甘さ=果糖は、やっぱりぜんぜん違いますよね。
みりんの代用品を手作りする場合の注意点
みりんは家にあるアルコールと糖類で、十分に代用可能です。



でも、ちょっと待った!みりんの代用がエスカレートして、みりんを作ってしまったら…それは法律違反です。
アルコール度数が1%以上の液体は酒類に該当するので、みりんは立派な「酒類」です。
酒類は、酒税法で手作りすることが禁止されています。
例外として、梅酒などのように酒税が課税済みのアルコールを使って混ぜるだけなら、製造したことになりません。
焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
引用:(※1)自家醸造|国税庁
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。



とてもややこしいけど、とにかくみりんは作ろうとしちゃダメってこと!日本酒で代用する分にはOKです。それでは具体的にみりんの代用レシピをご紹介しましょう。
おすすめ!日本酒+はちみつ
みりんの代用品として、いちばん味が近いと言われるのが、日本酒とはちみつのコンビです。
【材料】
日本酒:大さじ1(15g)
はちみつ:小さじ1(4g)
【作り方】
日本酒とはちみつを上記の分量でよく混ぜる。
日本酒は前述したように、みりんととても近いアルコール。
そこに足す糖類として、砂糖やはちみつが考えられますが、糖類の成分がよりみりんに近いのははちみつです。
はちみつ
=ぶどう糖、オリゴ糖、果糖、ショ糖などいろんな種類の糖が混ざっている
精製された白砂糖
=ショ糖のみ
みりんに含まれる糖類は、発酵の過程で作られている糖類なので、精製された白砂糖のようにシンプルではありません。
はちみつと同じように、ぶどう糖、オリゴ糖、果糖、ショ糖などがミックスされています。



このはちみつの雑多な感じが、みりんのそれととても近いんです。さらにショ糖よりもコクが強いぶどう糖が含まれるので、甘味だけでなくコクも追加できるよ。
ただし、はちみつは砂糖よりも甘みが強く、入れすぎると甘くなりすぎてしまうので気をつけましょう。
定番&簡単!日本酒+砂糖
みりんの代用品として、いちばん作りやすいのは、日本酒と砂糖のコンビです。



はちみつが家にない時は、砂糖でも代用OKです。はちみつはなくても、砂糖はある人が多いんじゃないかな…?
【材料】
日本酒:大さじ1(15g)
砂糖:小さじ1+1/2(4.5g)
【作り方】
日本酒と砂糖を上記の分量でよく混ぜる。
日本酒自体の甘さは個体差があるので、味を見ながら割合を決めるのがベスト。



上記はあくまで目安として考えてみてください。
はちみつと砂糖と日本酒は、それぞれ同じ重さ当たりの体積が違います。
日本酒大さじ1杯に対して、はちみつなら小さじ半分強で、砂糖は1杯半強!量には注意してみてね。
みりんも日本酒もない場合の代用品【難易度:中】


みりんは日本酒とそっくりなので、日本酒があるときは日本酒をベースにすれば問題ありません。
しかし、もしみりんも日本酒も両方ない時は、どんな調味料で代用するのが良いのでしょうか?
おすすめの組み合わせは以下のとおりです。
一つずつ見ていきましょう。
料理酒+砂糖・はちみつ
料理酒は日本酒とアルコール度数がほぼ同じため、砂糖やはちみつなどの糖類と混ぜればみりんの代用調味料として使用できます。
ただし、注意しないといけないのは、その塩分。
市販の料理酒には、だいたい3%程度の塩分が含まれています。
これは調味料として日常的に使う酒に酒税をかけず、安く販売するための打開策。
塩を入れて飲料用として販売できないようにすることで、安く販売することが可能になります。
第二条 この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
引用:(※2)酒税法第二条



安いのはうれしいけど、みりんの代用品にする時は塩分の摂り過ぎに注意が必要!
みりんの代用品として使う時は、その料理の塩分をひかえめにしましょう。
白ワイン+砂糖・はちみつ
白ワインも日本酒と同じくらいのアルコール度数の商品を見つけてくれば、みりんの代用調味料として使用できます。



でも白ワインは、モノによって全然味が違うので、みりんの代用にするのは難しい場合も多く、味見はマスト!そして少し糖類の割合を減らすのがポイントです。
白ワインを使うなら、なるべく癖がなく、甘すぎないもの、酸味が強すぎないものを選びましょう。
焼酎+砂糖・はちみつ
焼酎も日本酒と同じくらいのアルコール度数に変化させれば、みりんの代用調味料として使用できます。
焼酎のアルコール度数は、酒類の中でもかなり多い20%以上です。
日本酒やみりんは14%ですから、代用調味料にするならしっかりとアルコールを飛ばす必要があります。



焼酎はアルコールを飛ばすとうま味が多い液体になります。煮物料理によく使われるよ。
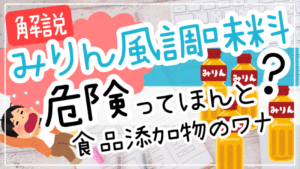
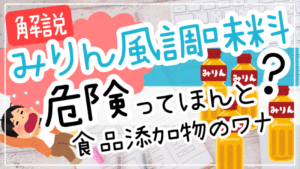
みりんも日本酒もアルコールもない場合の代用品【難易度:高】


最後にもっとも難しいと言われる、日本酒も、日本酒以外の酒類も一切ない場合におすすめの代用品をご紹介しましょう。



ここからは、若干味の変化がある可能性もあります。笑
一つずつ見ていきましょう。
コーラ
意外かもしれませんが、実はコーラはみりんの代用品になりえる食材のひとつ。
糖類のほかに、カラメル色素や香料を加えているため、独特なコクがあり、カレーやシチュー、煮込み料理などの隠し味によく使われます。
「コカ・コーラ」は、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、炭酸、カラメル色素、酸味料、香料およびカフェインからできています。
引用:(※3)よくある質問|コカ・コーラ
きりっとした単純な甘さの砂糖よりはみりんに近く、コクに特徴があります。
炒め物や焼き物には不向きですが、煮物料理にはよく合います。



もしコーラが余っていたら、ぜひ一度みりんの代用に挑戦してみて!
めんつゆ
めんつゆは、そのまま使える万能な調味料。
みりんの代用というよりは、出汁+みりんの代用になってしまうかもしれませんが、めんつゆさえ入れておけばマズくなることはないというぐらい、信頼性が高い調味料です。
しょうゆ(小麦・大豆を含む、国内製造)、ぶどう糖果糖液糖、食塩、砂糖、かつおぶしエキス、ふし(かつお、そうだかつお)、たん白加水分解物、醸造酢、魚介エキス、酵母エキス、デキストリン / 調味料(アミノ酸等)、アルコール
引用:(※4)めんつゆ 500ml|ヤマキ



いろんな材料が入っているなぁ…だしに砂糖に、アルコールも…!
水分量が多いので、こちらも炒め物等に使うのは難しいですが、煮物料理なら確実に美味しくしてくれるはずです。
みりんを使う目的・料理によって代用品は変わる


みりんを料理に使う時、私たちはいろんな目的を持っています。
そして、目的によって代用品として適した調味料が異なります。
例えば、甘みを追加する目的でみりんを使うなら、砂糖やはちみつで代用できるかもしれません。
一方で、煮くずれを防ぐ目的でみりんを使うなら、砂糖やはちみつを入れても意味がなく、酒類のアルコールで代用する必要があります。
みりんを使う目的別にみてみましょう。
やわらかな甘みがほしい場合
みりんには、発酵食品独特のやわらかい甘みがあります。
この柔らかい甘みは、白砂糖ではなかなか出すことができません。
そんな時、重宝するのが甘酒です。甘酒の糖類は、オリゴ糖やぶどう糖が多く、みりんの糖類と似ています。
白砂糖=ショ糖
みりん・甘酒=ぶどう糖、オリゴ糖、ショ糖、果糖など種類が豊富



発酵調味料は成分が多くなりがちです。
柔らかい甘さを追加したい場合は、甘酒をみりんの代わりに利用してみてください。
しっかりした甘みがほしい場合
わかりやすい甘みがほしい場合に、みりんの代わりに使える調味料と言えば砂糖です。
さらにコクも追加したい時は、三温糖がおすすめです。
三温糖
=糖液(糖蜜)を繰り返し煮詰めて作った砂糖のこと
そして、甘さよりもさらにコクに全振りしたい場合は、メープルシロップを使うのもよい代用策です。
煮くずれを防ぎたい場合
煮物などの煮くずれを防ぐためにみりんを使おうとしているのならば、代用品は酒類の料理酒や日本酒を使うのがおすすめです。
煮くずれは野菜などの細胞壁を構成する多糖類のペクチンが、加熱によって溶けてしまうことで起こります。
このペクチンを溶けにくくするためには、アルコールが必要です。
臭みを消したい場合
魚や肉類の臭みを消すためにみりんを使おうとしているのならば、代用品は酒類の料理酒や日本酒を使うのがおすすめです。
酒類に含まれるアルコールによって、臭みを目立たなくすることができます。



いろんな用途に使えるみりんは、工夫次第でいろんな代用ができるよ。ぜひいろいろ試してみてね。
まとめ:みりんがない!代用法を徹底解説!日本酒がない時


みりんが家にない時は、日本酒+糖類で代用するのが基本です。
みりん=日本酒+糖類
他にもいろんな方法がありますが、いちばん難易度が低いのが日本酒をベースにする方法。
しかし、常に日本酒が家にあるわけではない人は、一体どうしたらいいのでしょうか?
おすすめの組み合わせは以下のとおりです。
さらに酒類がひとつも家にない場合に試してみたいのは、以下の2つ。
みりんや日本酒とは風味が異なりますが、これはこれで美味しくできるのが不思議です。
参考にしてみてね。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/










