【この記事で解決できるお悩み】
・納豆はなぜ混ぜるの?美味しくなる?栄養が増える?
・いちばん美味しくなるかき混ぜ回数は?



この記事では、こんなお悩みを解決します!
和食あさごはんの定番おかずと言えば、納豆。
「せっかく栄養満点の納豆を食べるなら、最大限まで体に吸収したい…。」
「さらに、美味しくないとイヤ。いちばんおいしい食べ方をしたい…。」
そんなことを考えて、とにかくたくさん混ぜようと試みる方がいるようです。
でも、果たして回数と美味しさ・栄養は関係があるのでしょうか?
そこで今回は、納豆を混ぜる回数と美味しさ・栄養の関係を徹底解説!
様々な実験結果を紹介しながら、納豆を混ぜる理由や、納豆を混ぜる際のベスト回数についても整理してみました。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/


この記事を書いた人:
腸活研究家 長谷川ろみ
発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら
納豆を混ぜる理由は?


納豆を混ぜる理由を聞いてみると、多くの方がこの2つのうちどちらかを意識して混ぜています。
一つずつ見ていきましょう。
栄養が増える?
納豆を混ぜる回数は、納豆に含まれる栄養素や有効成分の量と関係がありません。



おお…やはり…?
大手納豆メーカーのタカノフーズ株式会社は、そのよくある質問ページ(※7)の中で、「栄養価は混ぜる回数に影響は受けない」と、説明しています。
納豆を混ぜていくと、豆の周囲についた粘り成分が集まり、空気を含んで、舌触りがまろやかになってきます。美味しさはこの舌触りの変化による部分が大きいようです。糸を引かない方が好みの方もいらっしゃいますので、一概には言えません。自分だけの好みの回数を見つけるのも良いでしょう。 栄養価は混ぜる回数に影響は受けないと言われています。
引用:納豆について|お客様相談室|タカノフーズ株式会社



栄養価が増えないとしたら、やっぱり美味しくなるのかな…?
美味しくなる?
納豆は混ぜる回数によって、うま味が増す(=美味しくなる)という報告があります。
秘密は納豆のネバネバのもとである、「グルタミン酸」。
グルタミン酸
=アミノ酸の一種で、納豆の旨味のもと
もともと納豆のネバネバは、グルタミン酸が鎖のようにつながった「γ‐ポリグルタミン酸」でできています。
「γ‐ポリグルタミン酸」は鎖でつながれているので、ヒトの舌にあるミライと呼ばれる神経伝達組織に「おいしい」という刺激を与えることができません。
納豆を混ぜると、「γ‐ポリグルタミン酸」の鎖が壊れて、「グルタミン酸」が増えていきます。
そこではじめて、ヒトは「おいしい」と感じることができます。
この「グルタミン酸の増加」が、納豆を混ぜるとおいしくなると言われる理由です。
納豆を混ぜる
↓
グルタミン酸(うま味)の増加
↓
納豆がおいしくなる



グルタミン酸が増えると、うま味が増え、食感もふわふわと柔らかくなります。
納豆がいちばん美味しくなるかき混ぜ回数は、いろんな企業やメディアが実験をしています。
ここではいくつかの実験をご紹介します。
NHK「ためしてガッテン」流!納豆が美味しくなるかき混ぜ回数
NHK「ためしてガッテン」という番組の中で、納豆をかき混ぜる回数とうま味がいちばん増えるに関して、実験を行っています。
この番組では、北大路魯山人(きたおおじ ろさんじん)という美食家が提示した納豆のおいしい食べ方を、その孫弟子に当たる方に再現してもらったもの。
この実験によると、納豆がおいしくなるかき混ぜ回数は、合計424回であることがわかりました。
納豆がおいしくなるかき混ぜ回数=424回
さらに北大路魯山人の納豆の混ぜ方、タレを混ぜるタイミングには一定のこだわりがありました。



納豆を混ぜる回数だけでなく、混ぜ方にもこだわりがあったんです。
北大路魯山人の混ぜ方だと424回がベスト
1:納豆に何も加えずに305回かき混ぜる
2:醤油・付属のタレを入れる
3:さらに119回かき混ぜる。この間に、醤油を2、3回分けて入れる(合計で424回)
4:ネギと和ガラシを入れて完成



最初から醤油を入れないのが、納豆を美味しくする大事なポイント!
醤油を最初に入れない理由
納豆の大豆の粒の周りには、白い膜のようなものが付いています。
これは、一般的に「被り」と言われるもの。
被り
=アミノ酸や酵素、納豆菌などが混ざった、うま味成分のもと
先に醤油を入れてしまうと、この被りがとれてしまうので、うま味が少ない納豆になってしまいます。
まずは何も入れないでかき混ぜることで、全体にうま味成分がいきわたり、おいしい納豆ができるという仕組み。
この実験では、うま味を測定するために「ホルモール態窒素の変化」を測定しました。



ホルモール態窒素は、納豆メーカーなどが旨味の指標として使っているんだって。
精密機械:「味覚センサー」流!納豆が美味しくなるかき混ぜ回数
「味覚センサー」とは、食べ物の甘味、旨味、塩味、酸味、苦味の5種類の味の要素を数値で表すことができるセンサーのことを指します。
味覚センサーだと400回がベスト
この味覚センサーで、納豆のかき混ぜ回数とうま味の変化を調べたとのこと。
納豆のかき混ぜ回数を100回から100回刻みで、1000回まで増やしていき、これ以上増えない回数は400回であることがわかりました。
400回を過ぎると、納豆の粒がつぶれていくだけでうま味はぜんぜん増えていかなかったそうです。



北大路魯山人の納豆の混ぜ方も424回ということは…400回ぐらいがいちばんうま味が多いっていうことか…信ぴょう性ありますね。
300回以上は甘みの多い納豆になる?
また、農林水産省食品総合研究所が納豆を混ぜることで、どのくらいうま味成分と甘み成分が変わるか確認した実験でも同じく300回以上が最高値だったことがわかっています。
| 納豆を混ぜる回数 | アミノ酸 | 甘み成分 |
|---|---|---|
| 100回 | 1.5倍 | 2.3倍 |
| 200回 | 2.5倍 | 3.3倍 |
| 300回以上 | 変わらない | 4.2倍 |



混ぜる回数が300回以上になると、旨味より甘みのほうが増えるんだなぁ…
腸活研究家:長谷川ろみ流!納豆が美味しくなるかき混ぜ回数


実は腸活研究家として、わたくし長谷川ろみも400回まで納豆を混ぜてみたことがあります。



いちおやってみないと始まりませんからね…!
確かに400回混ぜた納豆は美味しかったですが、実は30回ぐらいからもうほとんど変わらないぐらいのおいしさをちゃんと感じられたので、毎回400回混ぜる必要があるかは…人によりそうです。笑
おすすめの混ぜ方(簡易版)なら30回がベスト
1:納豆に何も加えずに20回かき混ぜる
2:醤油・付属のタレを入れる
3:さらに10回かき混ぜる
4:薬味を入れて完成



わたしの納豆の混ぜ方、おすすめはコレ!毎回400回混ぜるのが面倒・疲れそうな方はぜひ!
ちなみに2017年に行われたおかめ納豆の「納豆サイエンスラボ」調査によると、日本人の納豆を混ぜる回数の全国平均は「25.98」回であることもわかっています。(※6)
納豆を混ぜる全国平均回数:25.98回
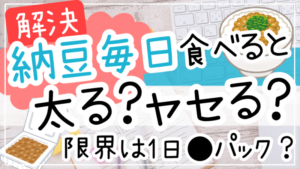
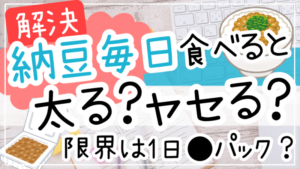
健康効果が気になる人へ!納豆を食べるタイミングを見直そう


納豆の健康効果は食べるタイミングによって、若干変わります。
ここでは、健康効果が期待できる納豆を食べるタイミングを2パターンご紹介します。
一つずつ見ていきましょう。
朝食べると、代謝アップに効果あり
シャキッと目を覚ましたい方やダイエット中の方は、納豆を朝食べるのがおすすめです。
朝、動き始めるタイミングで良質なタンパク質を補給すると、朝から体温が上がり、血行が良くなり、筋肉や臓器などを十分に働かせることができます。基礎代謝も上がります。
また納豆には、トリプトファンと呼ばれる必須アミノ酸が多く含まれています。
トリプトファン
=必須アミノ酸のひとつ
=大豆製品や乳製品に多く含まれ、幸せホルモン「セロトニン」の材料を作る
=安眠ホルモン「メラトニン」が正常に分泌されるのと助け、不眠を防ぎ、睡眠の質を上げる
トリプトファンを朝のうちにとっておくと、昼間に幸せホルモンの「セロトニン」を作ることができるので、精神的に安定します。
そして、その幸せホルモンの「セロトニン」が分泌されることで、安眠ホルモンの「メラトニン」も正常に分泌されやすくなります。
結果的に睡眠の質が上がり、自律神経が安定します。
夜食べると、血液老化を予防する
老化予防やアンチエイジングが気になる方におすすめのタイミングは、夕ごはんのタイミングに合わせて食べることです。
血栓を溶かす働きがあると言われるナットウキナーゼは、睡眠中に活発に働くと言われています。
そのもの株式会社が医師1032人に聞いた納豆に関する調査報告(※8)によると、ナットウキナーゼは就寝時に吸収しやすく、睡眠中にドロドロ化が進む血液中に血栓ができるのを防ぐ効果が期待されているとのこと。
・ナットウキナーゼは就寝時に吸収しやすい
引用:(※8)納豆に関する調査報告|そのもの株式会社
・睡眠中に血液がドロドロになりやすいのて、血栓予防には夜食べるほうが効果的
・体内消化がゆっくりだから
もし睡眠中に活発に働かせたいなら、その4~8時間くらい前に納豆を食べておきたいところです。



ちょうど夕ご飯のころに納豆を食べるのがよさそうですよね…
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/
かき混ぜ回数以外で栄養&美味しさを増やす納豆の作り方


ここからは、栄養価が高く人気の納豆をさらにおいしく食べるための方法を整理してみましょう。



選ぶ納豆やトッピングによっても、納豆の栄養素は大きく変わるよ。
一つずつ見ていきましょう。
納豆の種類
栄養価やうま味が多い納豆を選びたいなら、「粒納豆」より「ひきわり納豆」のほうがおすすめです。
大豆まるごと発酵させる「粒納豆」に比べて、皮を取り除いてから細かく砕いた豆を発酵させる「ひきわり納豆」は、皮の糖質がカットされるのはもちろん、発酵面が大きく栄養価が高くなりがちです。
「粒納豆」と「ひきわり納豆」の栄養成分表を比較してみると以下のとおりです。
| 粒納豆 | ひきわり納豆 | |
|---|---|---|
| エネルギー(kcal) | 190 | 185 |
| たんぱく質(g) | 16.5 | 16.6 |
| 脂質(g) | 10 | 10 |
| 炭水化物(g) | 12.1 | 10.5 |
| ナトリウム(mg) | 2 | 2 |
| カリウム(mg) | 660 | 700 |
| カルシウム(mg) | 90 | 59 |
| マグネシウム(mg) | 100 | 88 |
| リン(mg) | 190 | 250 |
| E(α-トコフェロール)(mg) | 0.5 | 0.8 |
| K(μg) | 600 | 930 |
| B1(mg) | 0.07 | 0.14 |
| B2(mg) | 0.56 | 0.36 |
| B6(g) | 0.24 | 0.29 |
| 食物繊維(g) | 6.7 | 5.9 |
ひきわり納豆は、粒納豆に比べて、カリウム、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1などが多めなので、体内の要らないものを体外に出すデトックス効果が高くなり、ダイエットやアンチエイジング向きと言えそうです。



すごく違いがあるわけじゃないけど、ひきわり納豆が好きな人はひきわりでもOK!なんとなくイメージで粒納豆のほうが栄養価が高そうって思っている人が多い気がするので、成分表を載せてみました。
納豆を混ぜる向き
納豆を混ぜる向きは、時計回りでも反時計回りでも、どちらでも構いません。
でも、一度かき混ぜはじめたら同じ方向でかき混ぜ続けるのがベスト。
なぜなら、途中で向きを変えることでうま味の成分が壊れてしまう可能性があるからです。



一度かき混ぜ始めたら、修行だと思って無心で同じ方向にかき回す…これが栄養価の高いおいしい納豆を作るコツなんですね。
納豆のトッピング
栄養バランスがよい納豆にしたいなら、納豆に不足しているビタミンCやビタミンB1の吸収が高まる硫化アリルが含まれたネギやにんにくがおすすめです。
硫化アリル
=ファイトケミカルの一種
=ビタミンB1と結びつき、吸収を高める



納豆は栄養バランスがよい食品だけど、どうせ何かを付け加えるなら、ビタミンCや硫化アリルが含まれたものをトッピングしよう!
ビタミンC
=海苔、パセリ、豆苗、ケール、高菜、モロヘイヤなど
硫化アリル
=タマネギ、ニンニク、ネギ、ニラ、ラッキョウなどに多く含まれる



比較的納豆と味のバランスがよいものが多くてうれしい!ネギや海苔はもう定番だよね。
みんなの納豆を混ぜる回数に関する口コミチェック!



納豆を混ぜる回数の好き嫌いは、人それぞれです。笑
まとめ:納豆を混ぜる理由を解説!回数によって栄養は変わるのか?


結論から言うと、納豆を混ぜる回数が多ければ多いほど、その栄養価や健康効果が増えるということはありません。
この理由は、納豆を混ぜれば混ぜるほど増える、ネバネバの正体に関連します。
納豆のネバネバの正体は、主に以下の2つの物質からできています。
➀グルタミン酸
=アミノ酸の一種でうま味のもと
=納豆に含まれるγ‐ポリグルタミン酸を納豆菌が分解するとできる
➁フラクタン
=糖の一種
混ぜれば混ぜるほど増えるのは、このグルタミン酸とフラクタンであり、健康効果よりもおいしさに大きくかかわる成分です。
多くの企業が納豆を混ぜる回数と栄養の関係について調査研究を行っていますが、現状はそこまで大きな影響はないというのが一般的な認識です。
栄養価が高く人気の納豆をさらにおいしく食べるための方法を整理すると、そのポイントは4つです。
納豆の種類
→粒納豆よりひきわり納豆を選ぶ
納豆を混ぜる回数
→424回混ぜる
納豆にタレを入れるタイミング
→最初からは入れない。ある程度ねばねばができてから入れる
納豆のトッピング
→ビタミンCや硫化アリルが含まれるネギやニンニクがおすすめ
納豆をはじめとする昔ながらの発酵食品は知れば知るほど、生活が豊かに、楽しく、時短になります。
参考にしてみてね。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/
参考文献
(※1)納豆は、よく混ぜる方がいいのですか?(ミツカン)
https://faq.mizkan.co.jp/faq/show/2963
(※2)味の素株式会社 うま味について
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/rd/reserch_output/umami/
(※3)グルタミン酸による消化管粘膜保護作用
https://yakushi.pharm.or.jp/FULL_TEXT/131_12/pdf/1711.pdf
(※4)Glutamic acid, the main dietary amino acid, and blood pressure: the INTERMAP Study (International Collaborative Study of Macronutrients, Micronutrients and Blood Pressure)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19581495/
(※5)Association of soy and fermented soy product intake with total and cause specific mortality: prospective cohort study
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m34
(※6)冬の感染症予防と納豆の健康効果についての意識調査(おかめ「納豆サイエンスラボ」)
https://www.atpress.ne.jp/news/142816
(※7)納豆について|お客様相談室|タカノフーズ株式会社
http://www.takanofoods.co.jp/contact/other.shtml










