【この記事で解決できるお悩み】
オリゴのおかげに危険性はあるの?ないの?
信頼できる根拠データもおしえて!
危険性がない&太らないためのおすすめの摂取法や注意点は?



この記事では、こんなお悩みを解決します!
1994年に「オリゴのおかげ」が全国発売されてから、なんともうすぐ30年。
近所のスーパーやコンビニでも入手しやすく、価格も比較的リーズナブルであることから、大人気のロングセラー商品となりました。
でも、一部のオリゴ糖を良く知らない人から見ると、「安価なのは危険性があるからでは…」と疑われているようです。
そこで今回は、オリゴのおかげに危険性があるのか、徹底解説!
科学的な根拠となる論文を踏まえながら、危険性がない&太らないためのおすすめの摂取法や注意点をご紹介します。
\ 日本初!5種類のオリゴ糖が入った機能性表示食品!(*´▽`*) /


この記事を書いた人:
腸活研究家 長谷川ろみ
発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら
オリゴのおかげの危険性を徹底解説!


まずは一部の方に疑われている、オリゴのおかげの危険性のポイントを整理してみましょう。
一つずつ見ていきましょう。
主成分の乳糖果糖オリゴ糖は危険?
オリゴのおかげの主成分は、乳果オリゴ糖(乳糖果糖オリゴ糖:ラクトスクロース)というオリゴ糖の一種です。
塩水港精糖株式会社の調査によると、乳糖果糖オリゴ糖は安全であることが確認されており、さらに下痢を発生しにくいオリゴ糖であることが報告(※1、※2)されています。



おお、よかった!危険性はないと考えてよさそう!さらに、無色透明で無着色・無香料なのもありがたいよね。
オリゴのおかげに使われている乳糖果糖オリゴ糖は、ガラクトース、ブドウ糖、果糖の3つの糖がくっついてできたオリゴ糖です。
| 別名 | 糖の数 | 糖の種類 | |
|---|---|---|---|
| ブドウ糖 | ー | 単糖類(=1個) | ー |
| 果糖 | ー | 単糖類(=1個) | ー |
| ショ糖 (一般的な白砂糖) | スクロース | 二糖類(=2個) | ブドウ糖+果糖 |
| 乳糖 | ラクトース | 二糖類(=2個) | ガラクトース+ブドウ糖 |
| 乳糖果糖オリゴ糖 (オリゴのおかげの主成分) | ラクトスクロース | 三糖類(=3個) | ガラクトース+ブドウ糖 +果糖 |
糖が1つだけの単糖類や2つくっついただけの二糖類は、消化吸収が早く、すぐにエネルギーに変化できる一方で、血糖値を急激に上げやすいと言われています。
しかし、オリゴのおかげの主成分である乳糖果糖オリゴ糖は、三糖類。
単糖類や二糖類と比較すると、胃や小腸では消化されにくく、大腸まで届き、腸内細菌のエサになります。
消化吸収が穏やかなので、血糖値も上がりにくく、大腸まで届いてから、腸内環境に変化をもたらします。



価格は安いけど、ちゃんと「難消化性(=消化しにくい)」なので、腸内細菌のエサになります。それも、善玉菌の一種である「ビフィズス菌」の大好物なんですよ。
オリゴのおかげの主成分である乳糖果糖オリゴ糖は、ビフィズス菌(Bifidobacterium)を増加させ、悪玉菌を減少させる働きがあることが報告(※3、※4)されています。



それも、1日たった1gしか食べていなくてもビフィズス菌が増えたから、すごいんです。笑
| 日付 | 摂取量 | 効果 |
|---|---|---|
| 1週間目 | 1g/日を摂取 | ビフィズス菌が優位に増加 (17.8%→38.7%) |
| 2週間目 | 2g/日を摂取 | ビフィズス菌が優位に増加 (38.7%→45.9%) |
| 3週間目 | 休 | ビフィズス菌が減少 (45.9%→18.2%) |
| 4週間目 | 3g/日を摂取 | ビフィズス菌が優位に増加 (18.2%→43.9%) |
(※4)もっと知りたい! オリゴ糖の特徴とその働き|株式会社パールエース
研究実験を開始より少しずつ乳糖果糖オリゴ糖の摂取量を増やしていき、3週目でいったん中止。
そして4週目で量を増やして再開したころ、乳糖果糖オリゴ糖を摂取したすべての週で、ビフィズス菌(Bifidobacterium)の増加が報告されました。
ビフィズス菌は、ヒトの腸内に生息する腸内細菌の中でも有名な善玉菌の一種です。
乳酸菌と同じように乳酸を作ることができるだけでなく、酪酸も一緒に作ることができるため、腸内環境内の短鎖脂肪酸を効率的に増やすことができるという特徴があります。



短鎖脂肪酸が多い腸を持つ人は、「太りにくい」、「病気になりにくい」、「老けにくい」などと言われているよ。
危険性がある添加物の含有量が多い?
オリゴのおかげの原材料は、「乳果オリゴ糖シロップ(国内製造)」のみであり、危険性の高い保存料、酸味料、人工甘味料などの添加物は入っていません。
名称:オリゴのおかげ
(※5)オリゴのおかげ300g|株式会社パールエース
原材料:乳果オリゴ糖シロップ(国内製造)
名称:オリゴのおかげ ダブルサポート 顆粒タイプ
(※6)オリゴのおかげ ダブルサポート(顆粒タイプ)|株式会社パールエース
原材料:乳果オリゴ糖顆粒(国内製造)
あくまで「乳果オリゴ糖」そのものではなく、「シロップ」と「顆粒」。
そのため、オリゴ糖が100%というわけではない点は、注意が必要です。



消化吸収されやすい乳糖やショ糖も含まれているので、まったく消化されない(血糖値を上げない)わけではないよ。
ショ糖=白砂糖に含まれる成分
乳糖=牛乳に含まれる成分
オリゴのおかげには、加工食品に多く含まれがちな保存料、酸味料、香料、着色料、人工甘味料などは含まれていません。
お腹がゆるくなりやすい甘味料だから危険?
オリゴ糖は、摂り過ぎるとおなかがゆるくなりやすいと言われています。
これは、オリゴ糖の一種であるオリゴのおかげの乳果オリゴ糖も同じです。
おなかがゆるくなる原因は、オリゴ糖が腸内細菌のエサとなり、腸内環境を活性化させてしまうから。
体質にもよりますが、ビフィズス菌が増えることで腸の蠕動運動が活発になりやすい人は、注意が必要です。
オリゴのおかげの商品パッケージに書かれた1日の摂取目安量は、「1日にティースプーンで2~5杯(8~20g)」です。



少なくともこの摂取目安量は守るようにし、自分の体への影響を感じながら調整していくのがおすすめです。
オリゴのおかげの乳果オリゴ糖は、他のオリゴ糖と比べると「下痢になりにくい」と言われています。
これは安全性検査でも確認できており、「体重50Kgの方の場合なら、30g/日までなら軟便化の傾向はみられなかった」という報告(※7)があります。
・30g/日を摂取した場合におなかがゆるくなる傾向がみられた
(※7)乳糖果糖オリゴ糖(ラクトスクロース)の詳細データ|オリゴのおかげ公式サイト
・最大無作用量は、男女ともに0.6g/kg (体重50Kgの場合:50Kg×0.6g=30g)



30g/日はさすがに食べ過ぎだと思うので、普通にコーヒーやヨーグルトに入れたり、料理に使う分には大丈夫かな?笑 人によるので、あくまで参考値として、注意しながら食べましょう。
太りやすい甘味料だから危険?
オリゴのおかげは、砂糖よりも甘さがひかえめで、カロリーが低く、血糖値も上げにくい甘味料です。
そのため、「太りやすい甘味料」というのは、一般的に考えて誤解です。
しかし、甘さがひかえめであるがゆえに、たくさん摂り過ぎてしまうリスクがあるので、注意は必要です。
ショ糖100%の白砂糖と比べると、カロリーの比較は以下の通り(※8)。
| オリゴのおかげ | 白砂糖 | |
|---|---|---|
| エネルギー | 230kcal | 393kcal |
| たんぱく質 | 0g | 0g |
| 脂質 | 0g | 0g |
| 炭水化物 | 72g | 100g |
| ナトリウム | 0㎎ | 0㎎ |
| 乳果オリゴ糖 | 30.2g | – |



やっぱり白砂糖と比べると、かなりカロリーはひかえめ…。甘さもひかえめなので、使う分量を増やしちゃうと意味がありません。笑
乳果オリゴ糖は、難消化性のためエネルギーになりにくく、血糖値も上げない甘味料です。
難消化性=エネルギーになりにくい=血糖値を上げない=太りにくい
そのため、食べ過ぎなければ太りにくいと言われています。


\ 特定保健用食品で信頼性バツグン!(*´▽`*) /
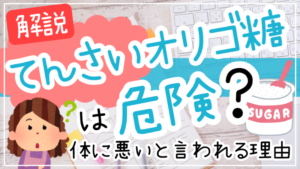
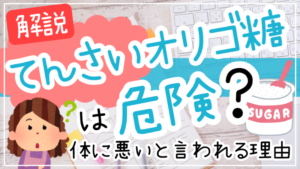
オリゴのおかげが信頼される理由


オリゴのおかげは、他のオリゴ糖と比較しても「信頼性が高い」と言われることが多い甘味料です。
その理由は、以下のとおり。
一つずつ見ていきましょう。
約30年のベストセラー商品である
オリゴのおかげは、実は発売からなんと約30年も愛されているベストセラー商品です。
その歴史は古く、最初に機能性オリゴ糖の研究を始めたのは1987年。
1991年に「乳糖果糖オリゴ糖」の家庭用卓上タイプの発売を開始し、1994年にその改良版となる「オリゴのおかげ」が生まれました。
そして翌年、1995年に「オリゴのおかげ」シリーズ全商品について、「特定保健用食品」表示許可(整腸作用)を取得しています。
「腸活」という言葉が一般的になった今では、多くのメディアがこぞって「オリゴ糖」の機能性を取り上げていますが、当時はまだそこまで認知度の高い言葉ではありません。



オリゴのおかげは、オリゴ糖業界の先駆者と言えそうです。大きな問題もなくロングセラーが続いているのは、愛されている証拠ですね。
特定保健用食品(トクホ)である
オリゴのおかげは、特定保健用食品(トクホ)として、国の許可を得た食品です。
市場に出回っているオリゴ糖関連商品の中でも、特定保健用食品(トクホ)として許可を得た商品は決して多くありません。
機能性表示食品
=事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品
(国は審査をしているわけではなく、消費者庁長官の許可もない)特定保健食品(トクホ)
(※9)機能性表示食品について|消費者庁
=健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、表示が許可されている食品
(国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/
(※10)特保(特定保健用食品)とは? | e-ヘルスネット(厚生労働省)
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-01-001.html



オリゴのおかげは、ちゃんと消費者庁が表示許可を認めている食品!危険性がないと信頼される理由のひとつです。
オリゴ糖の含有量が比較的多い
オリゴのおかげは、公式サイトにて乳糖果糖オリゴ糖含有量がきちんと明記されています。



他社のオリゴ糖関連商品の中には、そのほとんどがショ糖(白砂糖)や人工甘味料のものも多いよ。中にはそもそもオリゴ糖の含有量が明記されていない商品も…泣
オリゴのおかげには、以下の2つのシリーズがあり、シリーズによって乳糖果糖オリゴ糖含有量と甘さが異なります。
オリゴのおかげシリーズ


| 乳糖果糖オリゴ糖含有量 | 甘さ | |
|---|---|---|
| シロップタイプ | 30% | 砂糖の約80% |
| 顆粒タイプ | なし | なし |
\ 特定保健用食品で信頼性バツグン!(*´▽`*) /
オリゴのおかげ ダブルサポートシリーズ


| 乳糖果糖オリゴ糖含有量 | 甘さ | |
|---|---|---|
| シロップタイプ | 40% | 砂糖の約50% |
| 顆粒タイプ | 52% | 砂糖の約50% |
\ 特定保健用食品で信頼性バツグン!(*´▽`*) /
シロップタイプのオリゴ糖は、含有量が少なくなりがちです。
その代わり甘さが強いので、料理などに使いやすいというメリットがあります。
オリゴのおかげの場合は、オリゴ糖の含有量で選ぶなら、ダブルサポートシリーズの顆粒タイプがいちばん多くなります。



含有量だけじゃなく、使いやすさの問題もあると思うので、用途次第で使い分けるのがおすすめです。
オリゴのおかげの危険性を減らす選び方・食べ方


オリゴのおかげは、危険性が低い甘味料ではありますが、もちろんショ糖(白砂糖)なども含む甘味料です。
ショ糖(白砂糖)の摂取量をあまり増やしたくない方や、その機能性に興味がある方に向けて、
おすすめのオリゴのおかげの選び方・食べ方をご紹介します。
一つずつ見ていきましょう。
通常シリーズよりダブルサポートシリーズがおすすめ
オリゴのおかげのオリゴ糖の含有量や機能性は、シリーズごとに異なります。
家庭用のオリゴ糖の場合は、「オリゴのおかげシリーズ」と「オリゴのおかげ ダブルサポートシリーズ」の2つがあります。



実はこの「ダブルサポート」の意味が重要で…トクホの許可表示内容が2つ(ダブル)あるのが、ダブルサポートシリーズなんです。
オリゴのおかげシリーズの許可表示内容
乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つ食品です。
オリゴのおかげ ダブルサポートシリーズの許可表示内容
乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つとともに、カルシウムの吸収を促進する甘味料です。



おお。微妙に増えてる!笑
前述した、オリゴ糖の含有量も「オリゴのおかげシリーズ」が30%に対し、「オリゴのおかげ ダブルサポートシリーズ」は40~52%なので、より高い機能性を求める方には、「オリゴのおかげ ダブルサポートシリーズ」がおすすめです。
シロップタイプより顆粒タイプがおすすめ
「オリゴのおかげ ダブルサポートシリーズ」の中でも、さらにオリゴ糖の含有量がいちばん多いのが、顆粒タイプです。
コーヒーや紅茶に入れる、ヨーグルトに入れるなど、少量ずつ日常使いをする場合は、顆粒タイプがおすすめです。



個人的にはシロップだとついつい使いすぎてしまう感じがしたので、わたしは顆粒タイプが好きでした…笑 使いすぎなければいいだけの話なんだけどねw
加熱調理も可能!だが長時間加熱には注意
オリゴのおかげの乳果オリゴ糖は、熱に強く、加熱料理に使うことも可能です。



例えば熱いホットコーヒーに入れたり、トーストにジャム替わりに塗って焼いても、オリゴ糖はかんたんには壊れません!
しかし、あまりに長時間加熱する煮込み料理やジャムづくり、スイーツづくりにはあまり向いていません。



熱に強いとはいえ…全く変性しないとは言い切れないですよね…
製造日から1年以内に食べきろう!
オリゴのおかげの賞味期限は、製造日から1年です。
1年以内に食べきれるように、適量を購入するようにしましょう。
見た目は同じでも、保存状態によっては、同様の効果が受けられなくなる可能性があります。


オリゴのおかげを摂る際に気を付けること


オリゴのおかげに危険性がないことはわかりましたが、実際にオリゴのおかげをとる際に気を付けたほうがよいことをまとめてみました。
一つずつ見ていきましょう。
1日の摂取目安量を超えない(摂り過ぎない)
オリゴのおかげにリスクがあるとすれば、摂り過ぎによるリスクです。
体重50Kgの方の場合なら、30g/日以上とるとおなかがゆるくなる可能性があることも報告されていますし、そもそも糖質のとりすぎはよくありません。
WHO(世界保健機構)が2015年に発表した「成人及び子どものための糖類の摂取に関するガイドライン(※12)」によると、糖類の摂取量は1日の総エネルギーの10%未満が適切とのこと。
これはオリゴ糖だけでなく、糖類全般の摂取量を約25g/日におさえる必要があるということです。
オリゴのおかげは1日8gまで、糖類全般の摂取量はオリゴのおかげも含めて約25g/日におさえるようにしましょう。
お腹がゆるくなるようなら摂取を控える
いくらオリゴのおかげの1日の摂取目安量を守っていても、ヒトの腸内環境には個人差があります。
「1g/日しかとっていないのに、なんとなくおなかが張るような気がする…」と感じる人ももちろんいらっしゃいます。
人によっては早めにおなかが緩くなってしまう可能性もあるので、あまりあわないと思ったら違う種類のオリゴ糖や他の腸活食に切り替えるのがベスト。
ムリせず、自分にあった腸活法をみつけましょう。
オリゴのおかげだけでダイエット効果を求めない
あたりまえですが、オリゴのおかげはやせ薬や下剤ではありません。
下痢になるからと言って、食べ過ぎた時に大量に食べるようなことをしていては、明らかに腸に負担をかけます。
甘味料だけでダイエットをしようとすると食事に偏りがでるし、そもそも糖質の摂り過ぎに。
糖質はそんなに多く摂る必要はないので、あくまで白砂糖(ショ糖)などの置き換えとして考えるのがベターです。
オリゴのおかげはカロリーがゼロという誤解も多いですが、ゼロではないのも注意が必要です。
【特徴】
・消費者庁に届出され、便秘傾向者の便通を改善する機能がある「機能性表示食品」として受理
・全国売上日本一のオリゴ糖(日本能率協会総合研究所調べ)
・有名雑誌「anan」のカラダにいいもの大賞、2年連続受賞
・ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン配合
\ 日本初!5種類のオリゴ糖が入った機能性表示食品!(*´▽`*) /
オリゴのおかげを利用している方の口コミ・評判をチェック!


最後に実際にオリゴのおかげを利用している方の口コミや評判をチェックしてみましょう。
一つずつ見ていきましょう。
便秘予防に効果的
いちばん多かった口コミは、やはり便秘予防に効果的というご意見です。
オリゴのおかげのトクホの許可表示内容は、以下の通り。
乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つ食品です。



まさに、許可表示のとおりの効果を感じている方が多いようですね。
味にクセがないので使いやすい
はちみつやメープルシロップに比べて、味にクセがないので使いやすいというご意見も多くありました。
ダノンビオとの相性がよい
なぜか、ヨーグルト「ダノンビオ」と一緒に食べている人多数!ダブル効果を感じている方が多いようです。
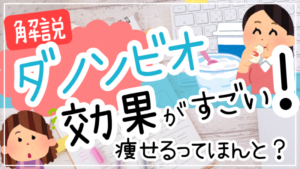
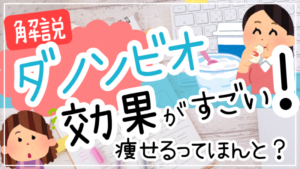
飲みすぎるとおなかがゆるくなる
ある意味いちばん心配されている危険性=おなかがゆるくなるを感じている方もいらっしゃいました。
甘さは砂糖に比べて弱い(入れすぎ注意)
甘さが弱いため、砂糖の置き換えにならないという方も。この機会に弱い甘さに慣れることも検討する必要がありそうです。
慣れてしまうと効果が薄れてしまう
どんな腸活食品でも同じですが、オリゴ糖も慣れると効果を感じにくくなるようです。
シロップタイプのボトルが使いにくい
ぶしゃーっと出ないように気をつけましょう。
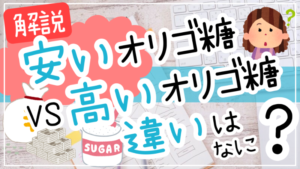
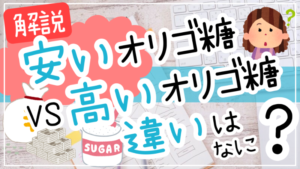
まとめ:オリゴのおかげに危険性はない?根拠データを解説!太らないための摂取法


オリゴのおかげに深刻な危険性はありません。
むしろ、オリゴのおかげは信頼性の高いオリゴ糖として、約30年間もロングセラー商品として売れ続けています。
一部の方に疑われている、オリゴのおかげの危険性のポイントは以下のとおり。
オリゴのおかげの主成分は、乳糖果糖オリゴ糖。
腸まで届き、腸内環境を整えることが期待されるオリゴ糖で、血糖値を上げにくいことから使い勝手の良い甘味料として重宝されています。
また、香料や着色料、保存料や人工甘味料も使用されておらず、他のオリゴ糖と比較しても「信頼性が高い」甘味料です。
信頼性が高い理由は、以下のとおり。
オリゴのおかげに危険性はありませんが、そもそも糖質の食べ過ぎはよくありません。
摂り過ぎないことはもちろん、体に合わないと思ったらすぐに摂取をやめましょう。
オリゴ糖には、いろんな種類があります。
どのオリゴ糖が自分の腸に合うかはわからないので、複数のオリゴ糖が入った商品のほうが体に合う可能性が高くなる可能性あり!
一度に多くのオリゴ糖をとって、いろんな種類の腸内細菌にエサを届けたい方は、「カイテキオリゴ」もおすすめです。
参考にしてみてね。
【特徴】
・消費者庁に届出され、便秘傾向者の便通を改善する機能がある「機能性表示食品」として受理
・全国売上日本一のオリゴ糖(日本能率協会総合研究所調べ)
・有名雑誌「anan」のカラダにいいもの大賞、2年連続受賞
・ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン配合
\ 日本初!5種類のオリゴ糖が入った機能性表示食品!(*´▽`*) /
参考文献
(※1)ラクトスクロース摂取と胃腸症状との関係-最大無作用量に関する考察
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jag1972/40/1/40_1_15/_article/-char/ja/
(※2)乳糖果糖オリゴ糖(ラクトスクロース)の詳細データ|塩水港精糖株式会社
http://www.oligo.jp/products/nyuka_oligo2.html
(※3)4G-β-D-Galactosylsucrose(ラクトスクロース)の少量摂取がヒト腸内フローラおよび糞便性状に及ぼす影響
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnfs1983/46/4/46_4_317/_article/-char/ja/
(※4)もっと知りたい! オリゴ糖の特徴とその働き|株式会社パールエース
https://www.pearlace.co.jp/know-and-fun/tips/post-47.html
(※5)オリゴのおかげ300g|株式会社パールエース
https://www.pearlace.co.jp/products/k10/4758701.html
(※6)オリゴのおかげ ダブルサポート(顆粒タイプ)|株式会社パールエース
https://www.okage-sama.co.jp/category/item_detail/pre-02.html
(※7)乳糖果糖オリゴ糖(ラクトスクロース)の詳細データ|オリゴのおかげ公式サイト
http://www.oligo.jp/products/nyuka_oligo2.html
(※8)日本食品標準成分表2020年版(八訂)
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html
(※9)機能性表示食品について|消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/
(※10)特保(特定保健用食品)とは? | e-ヘルスネット(厚生労働省)
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-01-001.html
(※11)商品・製品紹介|『オリゴのおかげ』シリーズ公式サイト
http://www.oligo.jp/products/
(※12)Sugars intake for adults and children|WHO
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149782/9789241549028_eng.pdf;jsessionid=704BA65BCF4313E76C6117F91530959D?sequence=1










