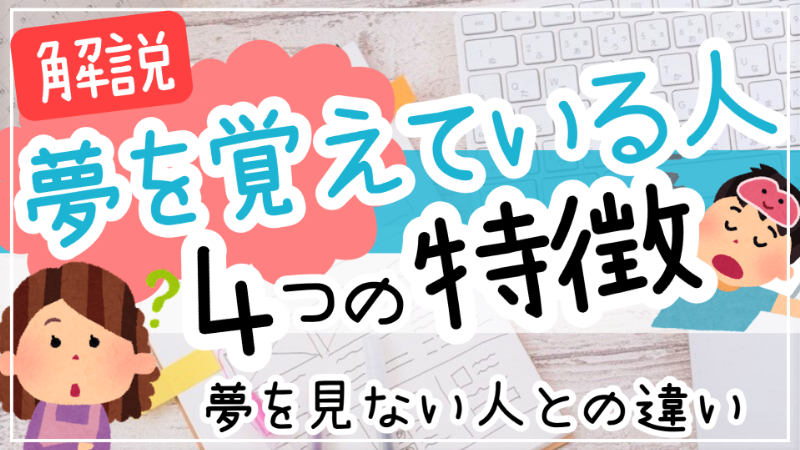【この記事で解決できるお悩み】
夢をよく覚えている人の特徴は?
ストレスが多いと夢をよく覚えているってほんと?
夢をよく覚えている人と覚えていない人の違いをおしえて!



この記事では、こんなお悩みを解決します!
誰もが寝ている時に見ている「夢」。
みんな同じように見ているハズなのに、よく覚えている人と全く覚えていない人がいます。
「ストレスがある人は覚えている」「睡眠の質が悪い人は覚えている」など、その原因について、ネットではいろんな憶測が…。
そこで今回は、夢をよく覚えている人と覚えていない人の違いを徹底解説!
科学的な根拠もご紹介しながら、夢をよく覚えている人の特徴を整理します。
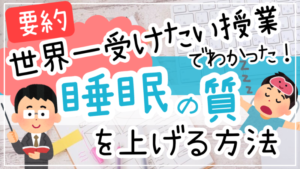
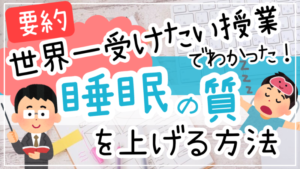


この記事を書いた人:
腸活研究家 長谷川ろみ
発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら
夢をよく覚えている人の特徴


夢をよく覚えている人のことを、社会学や心理学の専門分野では「高想起者(こうそうきしゃ)」と言います。
高想起者(こうそうきしゃ)=夢をよく覚えている人のこと
低想起者(ていそうきしゃ)=夢が記憶に残りにくい人のこと
高想起者には、科学的根拠に基づいた、いくつかの特徴があります。
一つずつ見ていきましょう。
年齢が若い
夢をよく覚えている高想起者は、高齢者よりも若者に多いという報告(※1)があります。
夢および悪夢想起頻度において、いずれも大学生や高校生の方が高齢者より多く、性差においては女性のほうが男性より多いが、性差は加齢とともに減少する結果となった
(※1)夢想起の発達差に関する研究
この研究では、大人になるにつれて記憶を検索する力が低下したり、忙しい日常の中で夢に対する興味が薄れるのが理由としています。



たしかに大学生の時は、友達と夢の話を良くした覚えが…今は、友達と夢の話をする機会はほぼないなぁ…。
夢は関心が強ければ強いほど覚えているもので、夢を覚えておくことを意識して眠るだけでも、想起しやすくなると言われています。
夢を見て、まだ記憶が鮮明なうちに文字に起こしておくことを繰り返していると、夢の中の出来事を意識して記憶したり、しっかり思い出そうとするようです。



夢占いが好きな人は、夢をよく覚えているというのと同じことですよね。私も若い時は夢の内容を手帳に書いていました。懐かしい…笑
女性である
2006年に法政大学で行われた研究(※9)によると、不安やストレスが高いと夢想起頻度も関連して高くなりますが、その際、男子よりも女子のほうが夢を覚えていることが多いことも分かりました。
【夢を覚えている順番】
不安高女子>不安高男子>不安低女子>不安低男子



女性のほうが不安を抱きやすいって言うから、なんとなく納得です。たしかに女性のほうが夢の話ってするよね。
理系より文系、クリエイティブな仕事をしている
夢をよく覚えている高想起者は、理系より言語化能力に慣れている文系に多い(※2)と考えられています。
もちろん個人差はありますが、夢を思い出すことができる能力と言語化能力は、比較的関連が大きいのだとか。



夢を覚えていて、ちゃんと想起できて、表現できるって考えると、確かに文系の人のほうが得意そう…イメージを膨らませることに長けているとも言えそうですね。
心配性でストレスを抱えやすい
夢をよく覚えている高想起者は、心配性でストレスを抱えやすい人に多いという報告(※3、※4)があります。
一般的な高想起者と低想起者の違いは、以下のとおり。
高想起者に多い性格・状態
=心配性、不安傾向が高い、情緒が不安定
=普段の生活でストレスを抱えている
低想起者に多い性格・状態
=のんびり、穏やか、現実的、情緒が安定
=ストレスに柔軟に対応できる
さらに想起する夢が悪夢(ネガティブな夢)である場合は、内向的でコミュニケーションが苦手な人が多い傾向にあるという報告も…。
悪夢(ネガティブな夢)をよく覚えている人
内向的な性格特性者
調和性の低い性格特性者
情緒不安定な性格特性者
良い夢(ポジティブな夢)をよく覚えている人
外向的な性格特性者
調和性の高い性格特性者
コミュニケーション能力が高い性格特性者
さらに悪夢(ネガティブな夢)をよく覚えている人は、昼間の活動にも以下の傾向があるとの報告(※3、※4)があります。
・主観的な睡眠の質が低下している
・精神的な苦痛やストレス、不安症状がある
・うつ病などである



一時的・短期的に夢をよく覚えていることが多くなったと感じたら、睡眠の質の低下やストレスと無関係ではないかも…しれません。
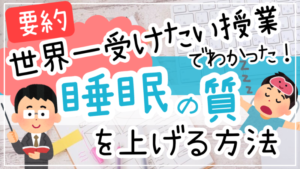
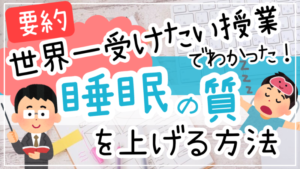
さらに、1997年に御茶ノ水女子大学で行われた研究(※8)をご紹介しましょう。
この研究では高校1年生125名に試験時と平常時に夢を覚えているかインタビューを行いました。
被験者:
高校1年生125名(男子70名:女子55名)
内容:
試験直前のストレスが多い時期と平常時に、夢を想起できるかを調査。
また試験にストレスを感じやすい群とストレスを感じにくい群の2つに分類。
➀夢を見たことは覚えているか?
➁その夢の内容を覚えているか?
結論:
人はストレスを感じている方が夢を覚えていることが多い
(ストレスを感じにくい人のほうが夢を覚えていないことが多い)
この研究によると、ストレスを感じやすい人のほうが夢を覚えていることが多いことがわかり、性格と夢の想起には関係があることがわかりました。
よく夢を覚えている人は比較的ストレスを感じやすく繊細で心配性で細やかであるという特徴があり、ネガティブな心理状態の時のほうが記憶しやすい可能性があります。
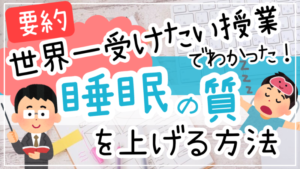
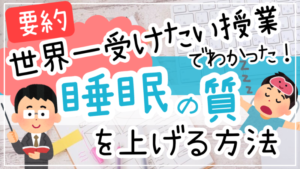
そもそも夢とは?どんな時に見る?


そもそも夢は、わたしたちみんなが寝ている間に見ているものです。
精神分析学の創始者として知られる「ジークムント・フロイト」の唱えた学説によると、夢は潜在的な願望が偽装されたものであると言われていますが、これもまだ専門家の間で議論が続いています。
一つずつ見ていきましょう。
レム睡眠(浅い眠り)の時に見る
きちんと記憶できる夢は、レム睡眠(浅い眠り)の時に見ていることが多い(※5)と言われています。
| 眠りの種類 | 全体の割合 | 眠りの深さ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| レム睡眠 | 睡眠全体の25% | 浅い眠り | 体は休んでいるが脳は活動的/記憶の固定や定着を行う 90分毎に現れて、5分から30分続く 一般的によく夢をみる |
| ノンレム睡眠 | 睡眠全体の75% | 深い眠り | 体も脳も休んでいる/記憶の結合や消去を行う 4段階に分かれ、いちばん深い睡眠を徐波睡眠と呼ぶ |
レム睡眠とノンレム睡眠は、どちらも大事な睡眠です。
レム睡眠ももちろん必要な睡眠で、動物実験ではレム睡眠を剥奪すると死に到るという報告もあるほどです。



あくまで睡眠全体のリズムが大切なんですね!
一晩に何回も見る
夢は、一晩に何回も見るのが普通です。
なぜなら、わたしたちは睡眠中にレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返し、その度に夢を見ていることが多いからです。
もちろん、そのすべてを覚えているわけではなく、基本的には目覚める直前のレム睡眠中に見た夢だけ。



レム睡眠中に起きると夢を覚えていることが多いですよね!
悪夢のほうが記憶に残りやすい
残念なのは、夢はポジティブな夢よりもネガティブな悪夢の方が、記憶に残りやすい(※1)ということです。
夢に出てくる言葉として私たちが想起できるものの多くはネガティブなもの。
追いかける
追う
走る
殺す
死ぬ
亡くなる
落ちる
飛び降りるなど



たしかにこういう夢を見た!ってよく聞く気がする…。
80歳以降は夢を覚えている機会が減る
80歳以降は、夢をよく見るレム睡眠の割合が減り、1回1回のレム睡眠の長さが短くなるため、夢を覚えている機会が減ると言われています。
さらに、高齢者の睡眠脳派を調べた研究(※6、※7)によると、高齢者は若年者に比べて深いノンレム睡眠が減り、浅いノンレム睡眠が増えるとのこと。



全体的に眠りの浅い部分と深い部分の差が小さくなるイメージなんですね…。
良い夢を見て覚えておく方法


良い夢を見て、さらにその夢を覚えておけるかどうかは、もともとの性格が大きく影響します。
しかし、普段の心がけ次第で、なるべく悪夢を見ないようにすることは可能です。
一つずつ見ていきましょう。
ストレスを溜めない・ストレスの素から逃げる
悪夢(ネガティブな夢)をよく覚えている人は、昼間の活動の中でストレスを溜めていることがわかりました。
交感神経が優位なまま、緊張が長く続いたり、ストレスがかかりやすいと感じる場合は、ストレスの素になっている出来事から積極的に逃げることもおすすめです。



逃げることは決して悪いことじゃないです。わたしもストレスから逃げただけで、体の不調が全部改善した経験があります。どんどん逃げよう!
ストレスを減らす食べ物を食べる
副交感神経を優位にして、リラックス効果を高めるホルモン「セロトニン」や、睡眠の質を上げるホルモン「メラトニン」を作りやすい栄養成分を積極的にとるのがおすすめです。
トリプトファン(必須アミノ酸)
ビタミンB6(ビタミン)
マグネシウム(ミネラル)
GABA(アミノ酸)
グリシン(アミノ酸)
オルニチン(アミノ酸)
サフラン(香辛料)
睡眠ホルモンのメラトニンを作るサポートをしたり、自律神経の緊張をほぐして質の良い睡眠にいざなうことができる食べ物を積極的にとりましょう。詳しくはこの記事も見てね。
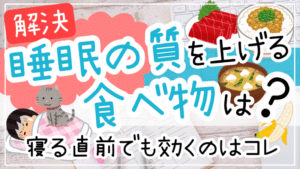
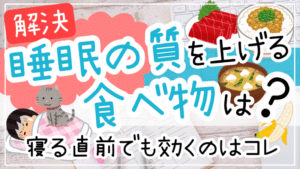
寝る前にネガティブ思考にならない環境を整える
入眠直前にネガティブな思考になると、どうしても悪夢の引き金を引きがちです。



寝る前に悪いことを考えていると、そのままそれが夢に出てきた経験、わたしもめちゃくちゃありますw
寝る前は余計なことを考えないように、リラックスできる寝室を作っておくのも大事なこと。
特に睡眠リズムが乱れやすい人は、寝る前にスマホを辞めるだけでも睡眠の質が向上する可能性があります。
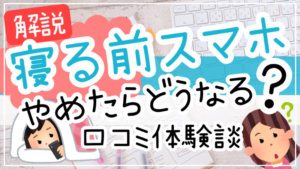
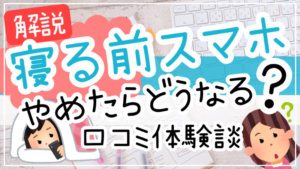
さらに、寝室を入眠しやすい環境に整えるためには、白い蛍光灯ではなく、赤っぽい暖かい光を使うのも効果があると言われています。
光は自律神経の切り替えに大きくかかわっていて、光によって自律神経をコントロールすることができます。
交感神経が優位になる=やる気モード=光を浴びる
副交感神経が優位になる=リラックスモード=光を弱くする
朝起きたらすぐにカーテンを開けて、交感神経が優位になるのをサポートしましょう。
同じ理由で、朝日を浴びるために朝の散歩を習慣にするのも有効です。
光を意識して、自律神経を整えることで自然な睡眠導入を心がけるのがおすすめです!



詳しくはこの記事も読んでみてね!
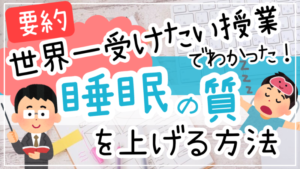
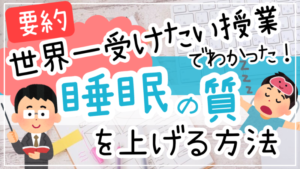
まとめ:夢をよく覚えている人の特徴は?夢を見ない人との違い
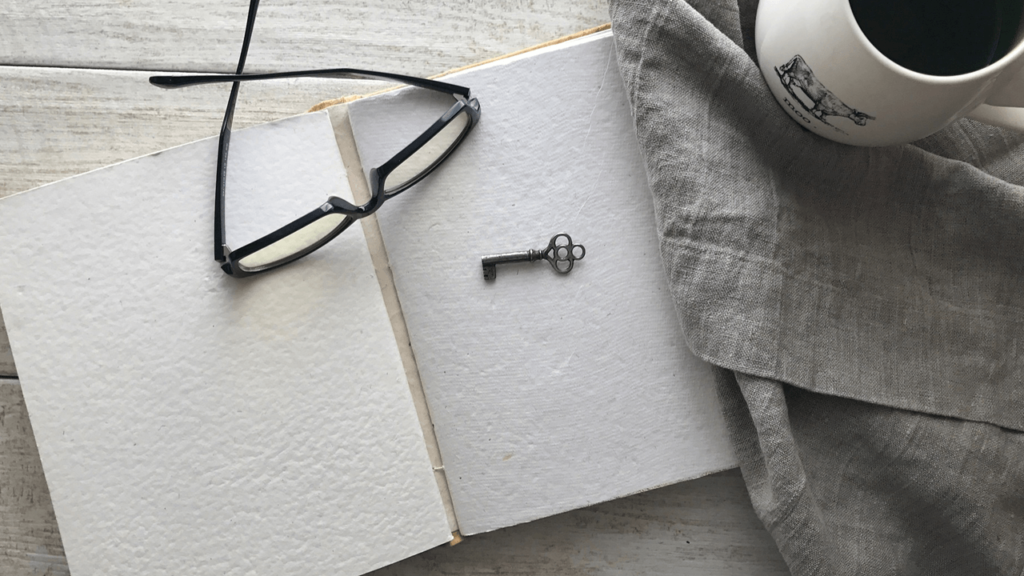
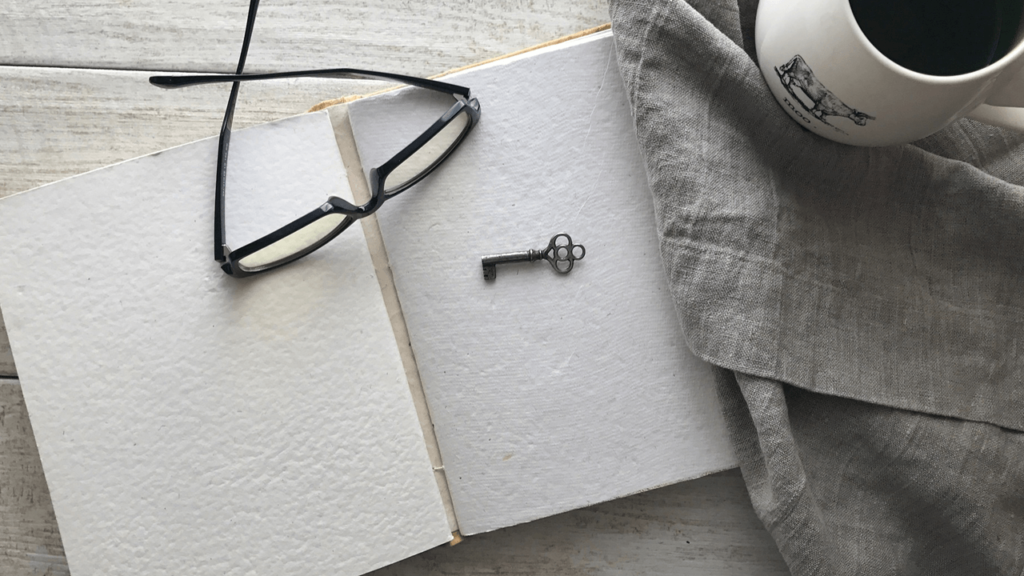
夢をよく覚えている高想起者には、科学的根拠に基づいた、以下の特徴があります。
夢をよく覚えているかどうかは、もともとの年齢や仕事、性格に依存する部分も大きいことがわかります。
しかし、想起する夢が悪夢(ネガティブな夢)である場合は、性格が内向的でコミュニケーションが苦手な人が多い傾向のほかに、短期的で心理的な問題がある可能性もあります。
・主観的な睡眠の質が低下している
・精神的な苦痛やストレス、不安症状がある
・うつ病などである
悪夢を見たくない人、よい夢だけを覚えいていたい人は、以下の対応策が有効です。
参考にしてみてね。
\ LDEライトを浴びるだけ!超簡単(*´▽`*)/
参考資料
(※1)夢想起の発達差に関する研究
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pacjpa/81/0/81_3B-023/_pdf
(※2)夢想起の頻度に人格特性とストレスーイベントが友ぼす影響
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpjspp/5/1/5_KJ00001287040/_pdf
(※3)Mental Sleep Activity and Disturbing Dreams in the Lifespan
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6801786/
(※4)夢想起の個人差に関する研究|ストレス科学研究 2012, 27, 71-79
https://www.jstage.jst.go.jp/article/stresskagakukenkyu/27/0/27_71/_pdf/-char/ja
(※5)睡眠|厚生労働省
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/alcohol/ya-034.html
(※6)高齢者の睡眠|厚生労働省
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-004.html
(※7)睡眠のメカニズム、生活習慣と睡眠|茨城県立健康プラザ
http://www.hsc-i.jp/05_chousa/doc/suimin_program/no5.pdf
(※8)夢想起の頻度に人格特性とストレスーイベントが友ぼす影響
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpjspp/5/1/5_KJ00001287040/_pdf/-char/ja
(※9)中学生の夢想起頻度に影響を及ぼす要因の研究 : テスト不安と性差の関係について
https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=4133&item_no=1&page_id=13&block_id=83