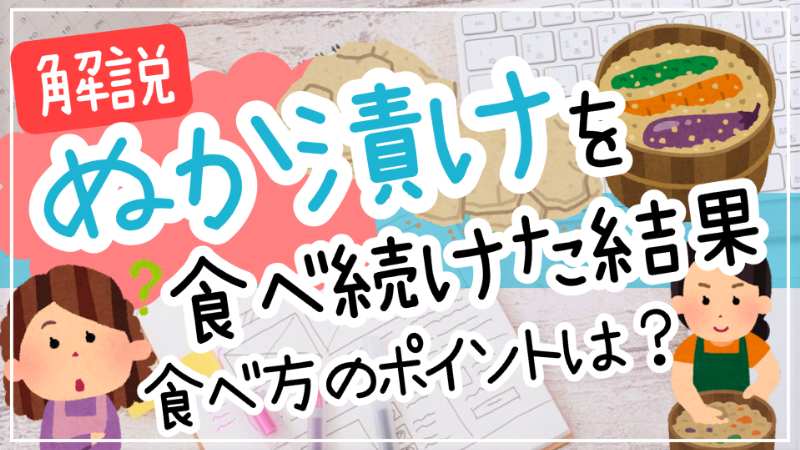【この記事で解決できるお悩み】
・ぬか漬けを食べ続けたら、どうなる?結果が知りたい!
・ぬか漬けで腸活するメリットとデメリットは?
・メリットを最大化するぬか漬けの食べ方は?



この記事では、こんなお悩みを解決します!
美容・健康意識が高い人たちの間で、ぬか漬けが再注目されています。
おうち時間の増加に伴い、手軽に始められるぬか床セットの販売が増え、ぬか漬けがより身近になったのが大きな理由。
そして何よりも、ぬか漬けを食べ続けた人たちにうれしい効果が出始めているからです。
そこで今回は、ぬか漬けを習慣的に食べるとどうなるのか、その結果を大調査!
腸活効果やデメリット、メリットを最大化する食べ方のポイントをまとめてみました。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/


この記事を書いた人:
腸活研究家 長谷川ろみ
発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら
ぬか漬けを食べ続けた結果どうなる?腸活効果は?


すでにぬか漬けを習慣的に食べている人の口コミを整理すると、以下の5つに分類できることがわかりました。
一つずつ見ていきましょう。
整腸効果・便秘解消
ぬか漬けを食べ続けた結果、整腸効果を感じたり、便秘が解消したという方が多くいます。



もともと便秘体質ではない私の友達も、排便回数が増えたらしい!私の場合は、特にオクラのぬか漬けの水溶性食物繊維がおなかに合うみたいです。笑
ぬか漬けには、野菜についている植物性乳酸菌のほかに、酪酸菌などのぬか由来の菌がたくさん!
さらに、同時に野菜の食物繊維がたっぷりとれるというメリットがあります。



発酵菌と善玉菌のエサ(食物繊維)を一度に両方採れるのは、かなり大きなメリットです。
野菜には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があり、それぞれ以下のような効果があることが知られています。
水溶性食物繊維
=水に溶ける食物繊維
=腸内に住む善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える
不溶性食物繊維
=水に溶けない食物繊維
=便のかさを増やし、腸の蠕動運動を活発にして老廃物を体の外に出す



水溶性食物繊維が多いオクラのぬか漬けが私はお気に入り!お腹がいつもすっきりしてて、ぽっこりお腹になりにくくなった!という方も多いよ。
美容効果
ぬか漬けを食べ続けた結果、肌がつるつるになったと美肌効果を感じている方もたくさんいます。
腸と肌(皮膚)はつながっているので、腸内環境を整え、炎症が起こりにくくなると、肌が安定します。



肌荒れやニキビ、吹き出物ができにくくなるっていう口コミ多数!
さらに、ぬか漬けに含まれるビタミンAやEが皮膚や粘膜の健康を保つ効果があることも、肌荒れ予防
ニキビ予防に貢献しています。
ぬか床に少なく、美容効果・抗酸化作用が高いビタミンと言えば、ビタミンC。
ビタミンCの多いパプリカなどの野菜を漬けることで、さらに、肌の水分量が安定します。



パプリカのぬか漬けも、さっぱりしてておいしいよ。


\ 失敗しないガイドブック&レシピ付き(*´▽`*) /
ダイエット効果
さらに、ぬか漬けを食べ続けたら、太りにくくなった、痩せた、体脂肪が減ったとダイエット効果を感じている方がたくさんいます…!



やっぱりぬか床を手に入れると、いろんな種類の野菜が気軽に食べられるようになるよね。
糖質代謝や脂質代謝を助ける栄養素と言えば、ビタミンB群。
ダイエット中に意識して摂りたい栄養素のひとつです。
野菜はぬか漬けにするだけで、栄養素が増えることが知られていますが、特にビタミンB1は10倍以上に増えるというから驚きです。
日本食品標準成分表2020年版(八訂)の生きゅうり、塩漬けきゅうり、ぬか漬けきゅうりの3種を比べてみると、以下のとおり。
| 生 | 塩漬け | ぬか漬け | |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 13kcal | 17kcal | 28kcal |
| たんぱく質 | 1.0g | 1.0g | 1.5g |
| 脂質 | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 炭水化物 | 3.0g | 3.7g | 6.2g |
| カリウム | 200mg | 220mg | 610mg |
| マグネシウム | 15mg | 15mg | 48mg |
| ビタミンB1 | 0.03mg | 0.02mg | 0.26mg |
| ビタミンB2 | 0.03mg | 0.03mg | 0.05mg |
| 食塩相当量 | 0g | 2.5g | 5.3 |



体の中のいらないものを捨ててくれるカリウムや、腸内環境を整えるマグネシウムも増えてますね!
ビタミンB群やミネラルのおかげで、代謝が上がり、体脂肪が蓄積しにくい状態になることから、健康的なダイエットに役立ちます。
免疫力アップ
ぬか漬けを食べ続けたら、免疫力がアップすることを感じている人もとても多いです。
なぜなら、ヒトの免疫細胞の7割は小腸に集まっているため、腸内環境が整うと免疫細胞の働きも正常化し、免疫力アップにつながることが知られています。
ぬか漬けの腸内環境改善効果が、結果的に免疫力アップにつながり、風邪やインフルエンザにかかりにくくなったり、花粉症やアレルギーが緩和します。



免疫細胞が正常に働いていれば、ガン細胞などもできにくくなるので、結果的に病気にもかかりにくくなると言われています。
ストレス解消
ぬか漬けにはGABAという成分がたくさん含まれているため、食べ続けるとストレス緩和効果を感じている人が多いことがわかりました。



それでもぬか漬けを作るのがめんどう…という方は、乳酸菌をサプリでとるのもひとつの手かも?!
\ 納豆菌と乳酸菌が一度にとれるサプリメントならコレ!(*´▽`*) /
ぬか漬けに含まれる注目の栄養素


野菜は生で食べるよりぬか漬けにすることで、ビタミンやミネラルが大きく増えます。
生食より大きく増える注目の栄養素は以下の通りです。
一つずつ見ていきましょう。
ビタミンB群
ビタミンB群は、ぬか漬けにすることで増える栄養素のひとつです。
特に大きく増えるのは、代謝を助けるビタミンB1とビタミンB2です。
ビタミンB1
=水溶性ビタミンの一種。炭水化物(糖質)の代謝を促す
=神経や筋肉の機能を正常に保ち、疲労回復に役立つ
ビタミンB2
=水溶性ビタミンの一種。エネルギー代謝を助ける。
=皮膚や粘膜を健やかに保つ
1996年に広島大学が報告した研究(※2)によると、ビタミンB1を摂取するだけで、軽度アルツハイマー病の患者の認知機能が改善したことがわかっています。
この研究で摂取したビタミンB1は1日100mg、継続期間は約12週間です。



いつまでも元気に若々しく生きていこうと思ったら、ビタミンB1が不足しないような食生活をキープするのも大事かも!食事のバランスは大事だなぁ。
カリウム&マグネシウム
カリウムとマグネシウムも、ぬか漬けにすることで増える栄養素です。
カリウム
=ナトリウム(塩分)の排泄をしてくれるミネラル
=高血圧やむくみを予防する効果がある
マグネシウム
=体内にある酵素(約300種類以上)のはたらきをサポートするミネラル
=カルシウムと一緒に丈夫な歯や骨を作る
=血糖値やコレステロール値の調整を行い、糖尿病の予防をする
マグネシウムは、体内にある酵素のはたらきをサポートするため、体のさまざまな機能に関わっていると言われています。
特に腸活中の方にとっては、腸内のぜん動運動を正常化し、腸内の水分量を適切にする効果もあるので、不足しないように注意したい栄養素の一つです。
また近年増えている糖尿病の予防になるという点も注目されています。
2006年にアメリカのハーバードメディカルスクールから発表された報告(※3)によると、マグネシウムのサプリメントを1日360mg、4週間~16週間にわたり摂取しただけで、空腹時血糖値が改善されたとのこと。
マグネシウムも不足しないように注意したい栄養素ですね。



わたしは白湯にマグネシウムがたっぷり含まれたにがりを、ちょっと追加して飲んだりしてます!入れすぎるとマズいから、気を付けて~笑
γ-オリザノール
γ-オリザノールは、米ぬかや米油に多く含まれるポリフェノールの一種です。
γ-オリザノール
=米ぬかに多く含まれるポリフェノールの一種。
=血行改善効果、コレステロール低減効果が注目されている
ポリフェノールは全般的に高い抗酸化力が注目されていますが、その中でも血中コレステロールを調整して、自律神経のはたらきを調整したり、動脈硬化を予防すると言われています。
γ-オリザノールはポリフェノールの一種で、高い抗酸化力があるとされている成分です。
血行をよくする作用や、悪玉コレステロールを減らし善玉コレステロールを増やすはたらきがあります。
また、自律神経のはたらきを助ける作用により、脳の機能の改善に役立つ成分でもあります。



ぬか漬けって、血行をよくしたり、コレステロールの調整をしてくれるので、慢性的な生活習慣病の予防になりそう…!お手軽なのに、うれしい栄養素がいっぱい採れます。
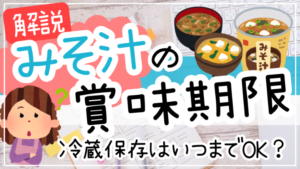
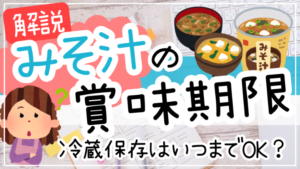
ぬか漬けの腸活効果


ぬか漬けは、数ある発酵食品の中でも群を抜いて、腸活向きの食材だと言われています。
その理由は以下のとおり。
一つずつ見ていきましょう。
生きて腸まで届く植物性乳酸菌の宝庫である
ぬか漬けに乳酸菌がたっぷり含まれていることは、みんな知ってのとおり。
しかしぬか床の中に生息する乳酸菌は、乳酸菌の中でも生命力が高いと言われています。
一般的に動物性乳酸菌より植物性乳酸菌の方が強い
塩分の多いぬか床に生息できる乳酸菌は強い



たしかに相当強い乳酸菌じゃないと、ぬか床の中には生息できないよなぁ…。
野菜の食物繊維がたくさん摂れる
腸活のためには、毎日十分な食物繊維を摂りたいところ。
食物繊維をたくさん摂るためには野菜が欠かせないのですが、野菜は腐敗するのが早く、毎日何かしらの調理が必要なため、忙しさにかまけて野菜不足に陥る方は少なくありません。
ぬか漬けがすごいのは、保存性が高いところ。
冷蔵庫に入れておいて、好きな時に取り出して食べられるので、無理なく野菜を習慣的に食べることができます。
さらに乳酸菌と食物繊維を一緒に食べることで、シンバイオティクス食材としても優秀です。
シンバイオティクス食材
=ビフィズス菌や乳酸菌などの発酵菌(プロバイオティクス)と一緒に、難消化性オリゴ糖や食物繊維など有用菌の増殖を促進するエサ(プレバイオティクス)を摂取することができる食材
ぬか漬けなら、毎日無理せず、シンバイオティクスな腸活ライフが送れそうです。
腸内細菌がビタミンを増やしてくれる
ぬか漬けに含まれる栄養素や食物繊維、菌体のおかげで腸内環境が整って、善玉菌と悪玉菌のバランスが良くなります。
すると、さらに腸内細菌たちがヒトの体を調整するためのビタミンやホルモンの材料を必死に作ってくれます。
単純に口から取り入れたビタミンやミネラルのほかに、体の中でも代謝のために必要な栄養素を自給自足できるようになるのです。



発酵食品がスゴイのは、この良い循環を作る手伝いをしてくれるところなんですよね。


ぬか漬けで腸活するメリット


ぬか漬けで腸活するメリットは、以下のとおり。
一つずつ見ていきましょう。
今すぐに始められる
昔のぬか漬けは、始める前にいろんな準備が必要で、面倒なものでした。
でも今は、ぬか漬けがかなり簡易化され、野菜を切って入れるだけの発酵ぬか床キットがたくさん売っています。



まずは、市販のぬか床キットで慣れ、アレンジしていくのがいいかも!
思い立ったらすぐに始められ、2~3日後には食物繊維と発酵菌を毎日食べられるのがぬか床の良いところです。
料理ができなくてもかんたんに作れる
ぬか漬けは料理ができない人でも、ぬか床を買うだけでかんたんに作れます。



わたしの友人でも料理をしないのにぬか床だけ持っている人がいます。スーパーで買ったおかずと手作りのぬか漬けを一緒に食べて、食事の栄養バランスをとっているんだって。
コンビニやスーパーで買うお弁当やおかずは、どうしても野菜が少なくなりがちです。
そんな時に冷蔵庫に常備してあるぬか漬けをちょい足しすれば、それだけでバランスの良い食事に近づかせることができます。



あと1品欲しい時に便利なのが、ぬか漬けです。
低額から始められてコスパが良い
ぬか床キットは、全部セットになっているものでも大体1000円前後で購入できます。



昔に比べると値段下がったよね…!
そこに気になる野菜を買ってきて、ぬか床にセットするだけなので、余計なキッチン用具も必要ありません。
他の腸活グッズよりもかなりお買い得なのが、ぬか漬けのメリットです。


\ 失敗しないガイドブック&レシピ付き(*´▽`*) /
ぬか漬けで腸活するデメリット


一方、ぬか漬けで腸活するデメリットは、以下のとおり。
一つずつ見ていきましょう。
管理が必要
最近のぬか床は、手間がかかりにくくなっていますが、それでも所有していると少なからず管理が必要です。
定期的にかき混ぜたり、水分量の調節をしたり、塩味や酸味が強くなりすぎないようにケアしたり。
おいしいぬか漬けを作り続けるためには、一定の管理が必要です。



最近は、何もしなくていいかんたんぬか床も売っているので、まずは簡易的なぬか床で慣れるのもひとつの手です。
酸っぱくなってしまったら、こんな方法で酸味を和らげましょう。
・重曹を入れる
・卵の殻を入れる(カルシウムを入れる)
・唐辛子や和がらし粉を入れる(乳酸菌の増殖を抑える)



詳しい管理方法は、このページでも紹介しています。気になる方は見てみてね。
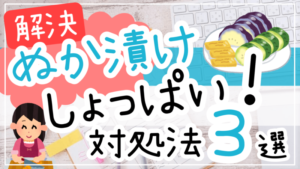
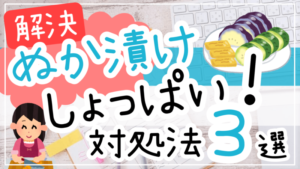
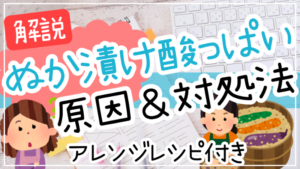
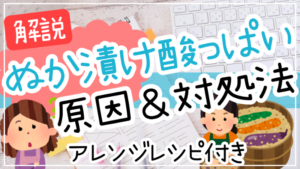
味やにおいに癖がある
ぬか床やぬか漬けは、酪酸菌がたくさん含まれていることもあり、味やにおいが独特です。
この独特なクセが得意な方はいいのですが、苦手な方も一定数いらっしゃいます。



好みが分かれやすいんですよね。
保管場所を確保する必要がある
ぬか漬けづくりを始めると、保管場所を確保する必要があります。



一人暮らしの方で、ぬか床の置き場所に困ってる人も多いよね…
熱がこもらず、直射日光も当たらず、清潔な場所に置いておくことが推奨されるぬか床ですが、誰もがそんな場所をかんたんに確保できる、広いキッチンが付いた家に住んでいるわけではありません。
人によっては、保管場所を新たに準備する必要が出てきます。
塩分の摂り過ぎに注意
ぬか漬けを食べる時に唯一心配なのが、塩分の摂り過ぎです。
ぬか漬けは生食に比べて、塩分量が多いため、食べ過ぎは禁物です。
継続的に食べ過ぎると、むくみを発祥したり、余分な塩分を排出しようとして腎臓に負担をかけたり、高血圧などの生活習慣病を発祥する可能性があります。
厚生労働省が提示する、日本人の食事摂取基準(2020年版)(※5)によると、日本人の1日の塩分摂取量の目安は、以下のとおり。
男性:7.5g未満(1食当たり2.5g)
女性:6.5g未満(1食当たり2.4g)
※食塩の摂取量は1食あたり2~2.5g程度
ぬか漬けを一切れ食べると、その塩分量は大体0.2~0.4g程度なので、バクバク大量に食べてしまうと、目安量をゆうに超えてしまうのです。



ぬか漬けの食べ過ぎは禁物です!
食べ過ぎると下痢になることも…!
めずらしいケースですが、ぬか漬けが体に合わない人もいます。
ぬか漬けにはたくさんの乳酸菌や酪酸菌が含まれているため、腸のぜん動運動を活発にしてしまい、もともと下痢症の方などは腹痛に見舞われることがあります。



体質に合わないなと思ったら、無理せずに食べるのをやめるのが賢明です。
メリットを最大化するぬか漬けの食べ方のポイント


ぬか漬けにはたくさんの美容、健康メリットがありますが、食べ方によっては逆効果になってしまう可能性があります。
メリットを最大化するぬか漬けの食べ方のポイントは、以下のとおり。
一つずつ見ていきましょう。
ぬか漬けの1日の摂取量の目安は?
ぬか漬けの1日の摂取量の目安は、毎日2~3切れがおすすめです。
1日の摂取量の目安:毎日2~3切れ(約20g)
ぬか漬けには菌体やビタミン、ミネラル、食物繊維がたっぷり含まれていますが、同時に塩分も含まれます。
厚生労働省が提示する、日本人の食事摂取基準(2020年版)が示す塩分摂取量の目安である1食当たり2.5g程度を目指すと、ぬか漬けを大量に食べるのはリスクが高い可能性が。
普段の食事バランス次第ではありますが、くれぐれもしょっぱいぬか漬けを大量に食べ続けるのはやめましょう。



ぬか漬けを細かく切って、塩などの調味料の代わりにするのも減塩法としてはおすすめです。塩分と一緒に菌体も摂れて一石二鳥だよ。
| 100g中の塩分量(g) | 3切れ分(20g)の塩分量(g) | |
|---|---|---|
| かぶ(皮付き)のぬか漬け | 2.2 | 0.4 |
| なすのぬか漬け | 2.5 | 0.5 |
| だいこんのぬか漬け | 3.8 | 0.8 |
| きゅうりのぬか漬け | 5.3 | 1.1 |
| かぶ(皮なし)のぬか漬け | 6.9 | 1.4 |



皮つきのかぶやなす、大根は塩分量1g程度に抑えられますが、きゅうりとか皮なしのかぶはやっぱりちょっとおおそう…塩分抜きが必要ですね!
ムリせず継続することを目指そう
ぬか漬け生活は、無理しないのが継続のコツ。
「毎日かき混ぜないといけない」「おいしくないといけない」などと、自分ルールを厳しくしてしまうと、ストレスになって、かえってよくありません。
最初はムリせず、市販のかき混ぜないぬか床を買ってきて、自分が好きな野菜を入れてみることから始めるのがベスト。
少しずつ疲れにくくなったり、肌つやが良くなったりしてきたら、自分に合ったぬか漬けライフを再検討するのがよいでしょう。
カリウムを含む野菜を選ぼう
ぬか漬け生活で唯一心配なのが、塩分の摂り過ぎであるとお話しました。
ぬか漬けの塩分をなるべく抑えるのはもちろんですが、摂ってしまった塩分を体の外に排泄しやすい体を作ることも大切です。
塩分を排泄するなら、カリウムの多い野菜を食べるのがおすすめ。
キュウリや大根、ナスなどはぬか漬けにしてもおいしいし、カリウムも同時にたくさん摂取できます。
皮はむかずに、皮ごと漬けよう
ぬか漬けを漬ける際に、キレイに皮をむく方がいます。
しかし、実はこの皮の部分に食物繊維やビタミン、抗酸化成分がたっぷり含まれています。
栄養学的な面からも理想的な食べ方として、「ホールフード(=まるごと食べる)」という考え方がありますが、ぬか漬けの時こそ、この考え方がおすすめです。



もちろん皮には農薬が付いていることを心配される方も多いので、無農薬野菜が手に入った時だけ、皮を残すみたいな考え方もありだと思います。
野菜を切らずに漬けよう
ぬか漬けを作るときに、意外と迷うのがどんな形にして漬けるかです。



たまに細かく切って小さくしてから漬ける人がいるけど、それはあまりおすすめではありません。
ぬか漬けはなるべく細かく切らずにそのまま漬けるのがおすすめです。
なぜなら野菜を細かく切ると、その断面からどんどん塩分が入り、しょっぱくなってしまうことが多いから。
減塩のおいしい漬物を作る場合は、あまり細かく切らずに、そのまま漬けたほうが程よく漬かります。
うま味成分を含む食材の量を増やそう
ぬか床生活に慣れてきたら、うま味成分が含まれている食材をぬか床にちょい足しするのもおすすめです。



このちょい足しがしょっぱくなりすぎるのを抑えてくれるよ!
例えば、昆布、かつお節、乾燥しいたけなどを少しいれるだけで、塩分を抑えて、水分量を調節してくれる可能性があります。



詳しいぬか床管理の方法は、この記事にも書いたよ。読んでみてね!


しょっぱかったら、水抜きしよう
ぬか漬けがしょっぱくなっちゃったらどうしよう・・・みんな気になる大きな問題ですが、最悪の場合、ぬか漬けは出来上がってから味を調整することもできるので大丈夫。
塩分が気になる場合は、ぬかから出した野菜を少し水に漬け、塩抜きすることも可能です。
漬けすぎるとおいしくなくなるので、5~10分程度漬けたら味を見てみるのがおすすめです。
まとめ:ぬか漬けを食べ続けた結果どうなる?腸活効果とデメリット


すでにぬか漬けを習慣的に食べている人の口コミを整理すると、こんなうれしい効果を感じている方が多いことがわかりました。
ぬか漬けにすることで、栄養素はぐんと増えますが、中でもビタミンB群やカリウム、マグネシウムの増加量は激しく、ビタミンB1はなんとほぼ10倍、カリウムやマグネシウムは3倍以上に増えるというから驚きです。
ぬか漬けで腸活するメリットとデメリットは、以下のとおり。
デメリットを最小化し、メリットを最大化するぬか漬けの食べ方のポイントは、以下のとおり。
参考にしてみてね。
発酵を体系的に勉強したくなったら…
発酵ライフ推進協会オンライン校へ
\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/
参考文献
(※1)日本食品標準成分表2020年版(八訂)
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html
(※2)Thiamine therapy in Alzheimer’s disease
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8815393
(※3)Effects of oral magnesium supplementation on glycaemic control in Type 2 diabetes: a meta-analysis of randomized double-blind controlled trials
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16978367
(※4)ぬか漬けが秘める力|京つけものもり
https://kyoto-mori.co.jp/gaba
(※5)日本人の食事摂取基準(2020 年版)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf